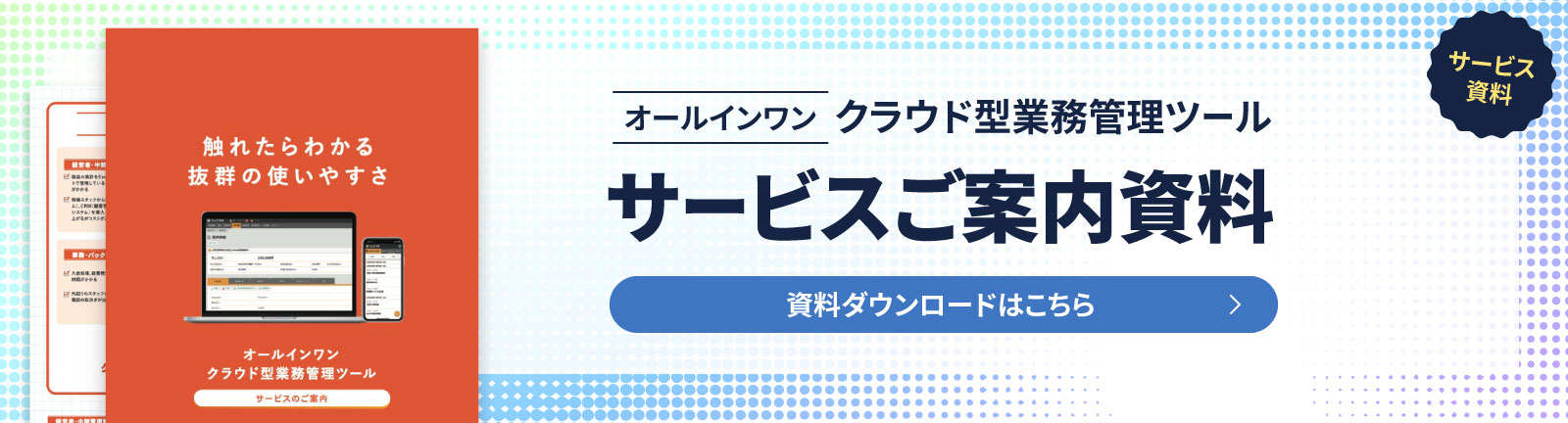インボイス制度とは?中小企業に与える影響やインボイス発行方法についてご紹介
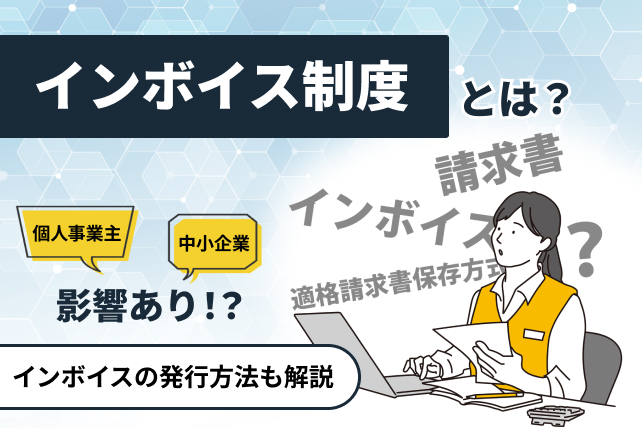
2023(令和5)年10月1日からスタートする「インボイス制度」の影響を大きく受ける可能性が高いのは、年間売上高が1,000万円以下の中小企業や個人事業主などです。そこで本記事では、インボイス制度の概要を確認しながら、インボイス制度がスタートした際の注意点や中小企業や個人事業主の対応方法などをまとめて解説します。
記事の内容
1. インボイス制度とは?制度がスタートする目的について
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、インボイス(適格請求書)のやり取りを通じ、インボイスを受け取った者のみ消費税の仕入れ税額所控除をできるようにする制度です。インボイス制度導入後は、仕入先などが発行するインボイスがないと消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。自社の発行する請求書がインボイスに対応していない場合、請求書を受け取った取引先は仕入税額の控除を受けることができません。
インボイス制度導入後は仕入税額の控除を受けるために、取引先は「インボイスを発行できるかどうか」を取引先選定基準として重視する可能性があることから、インボイスに対応していない場合、取引先から選ばれにくくなる可能性があるデメリットがあります。
インボイスとは?
インボイス(適格請求書)とは、正確な適用税率や消費税額などを売り手が買い手に対し伝えることを目的とした請求書のことです。現在義務付けられている「区分記載請求書」に以下3点の項目を追加した請求書がインボイス(適格請求書)になります。
1.適用税率
2.適用税率ごとの消費税額
3.インボイス制度の登録番号
インボイス制度の目的
消費税の申告や計算は手間がかかることもあり、これまでは課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者の申告や納税は免除されていました。
しかし導入当初の3%からだった消費税は10%になった現在でも免税事業者の消費税の申告や納税が免除されることから、課税事業者と免税事業者との間の「不公平感」が大きくなっていました。その「不公平感」を改善するために導入されるのがインボイス制度になります。
2. インボイス制度がスタートした後の対応と影響について
インボイス制度では、「課税事業者」と「免税事業者」それぞれで対応が異なります。事業者は以下のように区別されます。
課税事業者:消費税を納める義務を負っている事業者のこと
免税事業者:消費税を納める義務を免除されている事業者のこと
課税事業者の場合
課税事業者は仕入税額控除を行い、消費税を納付する必要があります。インボイス制度が始まった際は、仕入税額控除を行うために仕入先からインボイスを入手しなければなりません。取引先が免税事業者の場合、インボイスを入手できないため仕入税額控除ができません。そのため自己負担消費税として納税する必要があります。
インボイス制度開始から6年間は要件を満たした場合のみ経過措置が認められており、最初の3年(2026年9月30日まで)は免税事業者等からの課税仕入れの80%を、その後の3年(2029年9月30日まで)は50%を控除することができます。
免税事業者の場合
免税事業者はこれまでと同様に消費税の納付は免除されます。しかし取引先が課税事業者の場合、インボイスを発行することはできません。インボイスを発行できないことで取引先の課税事業者が仕入税額控除を受けることができず、取引先からの取引を見直される可能性があります。
インボイス制度が始まると、課税事業者・免税事業者それぞれ対応方法が異なるため、免税事業者はそのままでいるか、課税事業者になるか判断しなければなりません。
3. 中小企業や個人事業主は注意が必要!インボイス制度の注意点
注意点①:売上が減少する可能性がある
先述の通り、免税事業者は、課税事業者が仕事を発注する場合、免税事業者との取引は税負担の増加につながるため、取引を見直される可能性があります。また、取引が継続しても取引先は税負担が増加するため実質的な値引きを要求されることが考えられます。
注意点②:事務負担の増加、利益の減少が懸念される
免税事業者が課税事業者になれば、取引先は仕入税額控除ができるため、取引を継続してもらえる可能性が高くなります。しかし、消費税の納付が発生することから、その分を販売価格に転嫁できなければ、利益が減少するリスクがあります。また、消費税の計算・申告・納税事務などの業務負担が増加することが考えられます。
注意点③:取引先により影響の大きさが異なる
一般消費者を相手に事業を行っている免税事業者は、仕入税額控除は不要なので課税事業者にならなくても影響は少ないと考えされます。一方、事業者を相手に事業を行っている免税事業者の場合は、免税事業者のままでいることによるデメリットの影響が大きいと想定されるため、課税事業者になるか検討することが必要になります。
参考:中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策|日本商工会議所 中小企業振興部
4. インボイスの発行方法
インボイスの発行事業者になる予定の方は、事前に下記の準備が必要になります。
インボイス発行事業者に登録申請する
インボイスを発行することができるのは、税務署から承認を受けた「インボイス発行事業者」のみです。税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで適格請求書発行事業者として登録することができます。
現在の請求書などの様式を変更する
現在発行している請求書などのフォーマットをインボイスで必要な項目を記載したものに変更する必要があります。インボイスは、必要な事項が記載されていれば様式は自由です。手書きであっても、下記3つの項目が記載されていれば、インボイスに該当します。また、書類の名称も請求書や領収書、レシートなどどんなものでも構いません。
1.適用税率
2.適用税率ごとの消費税額
3.インボイス制度の登録番号
インボイス制度開始後は、発行側と受取側の両方が、請求書の控えを7年間保存することが義務付けられています。保存方法も、電子帳簿保存法により2024年1月1日以降は、電子データは印刷せずにデータのまま保存することが義務付けられています。
5. インボイス制度による事務業務負担の抑え方
インボイス制度により請求書に関わる事務作業が増えることが想定されます。発行時の作業として適用税率ごとに消費税額の計算を行う作業が増えてしまったり、受け取った際に登録番号に誤りがある場合は登録番号の確認作業に時間が掛かったりすることが想定されます。
また、インボイス制度は請求書の控えを7年間保存することが義務付けられていることから従来よりも扱う書類の量が増えることによる負担も想定されます。
このような事務負担を軽減するためには、インボイスに関わる書類発行の効率化や一元管理ができるITツールの導入がおすすめです。面倒な消費税額の計算や登録番号の反映を自動化し、効率的に請求書を発行できるツールを導入することにより、事務負担を軽減することができます。
6. インボイス制度への対応は、¥1,000~/月で利用できる「ジョブマネ」で
「ジョブマネ」は標準機能でインボイス制度に対応しています。面倒な適用税率ごとの消費税額の計算も自動で行うことができ、インボイス制度の登録番号も全ての請求書や納品書に自動反映されます。
「ジョブマネ」は¥1,000~/月で1名からご利用可能です。インボイス制度に対応した帳票の出力をお試しいただける30日間無料トライアルもございます。ご興味のある方はぜひ、トライアルをお試しください。