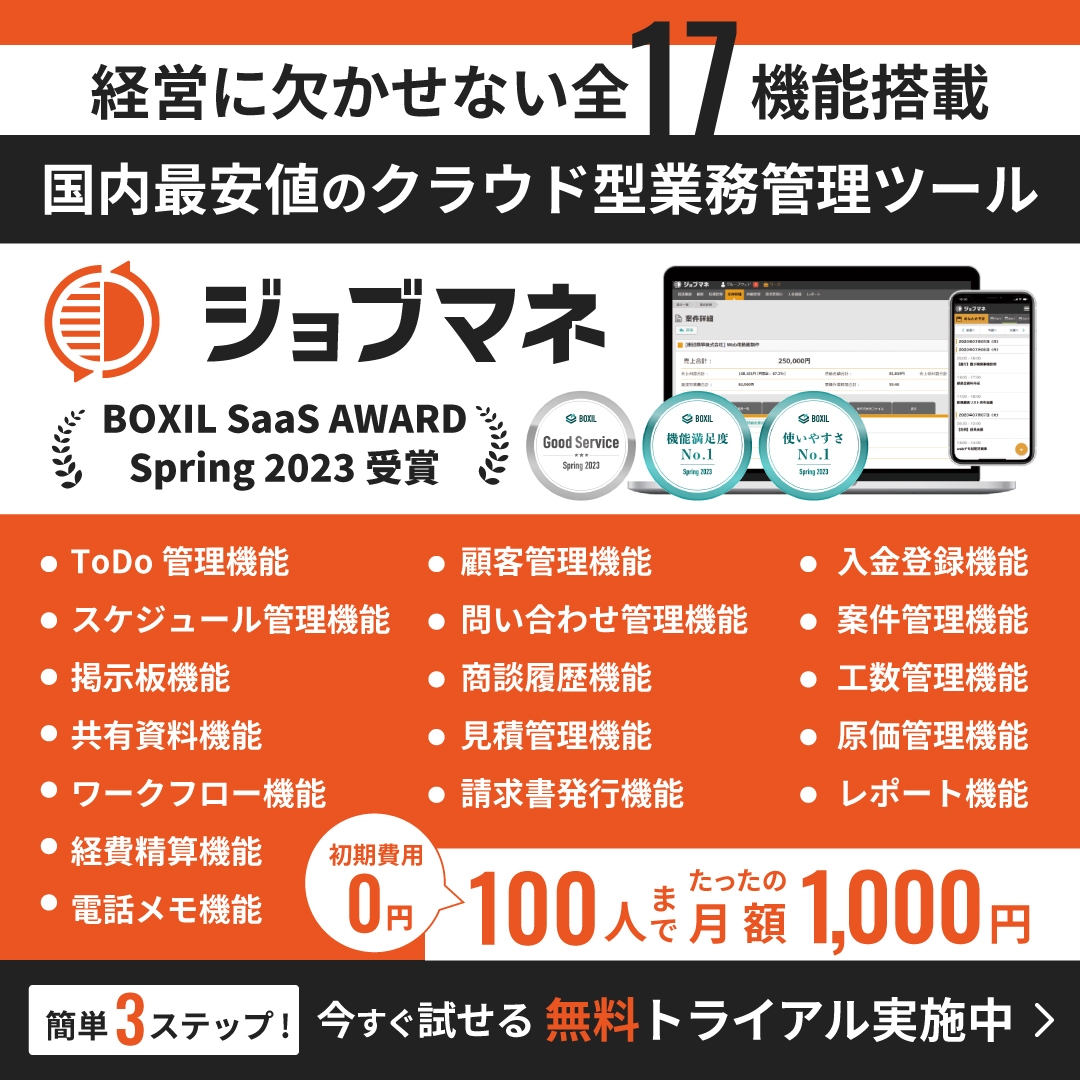売上予測とは?計算方法や予測精度を高める方法を解説!
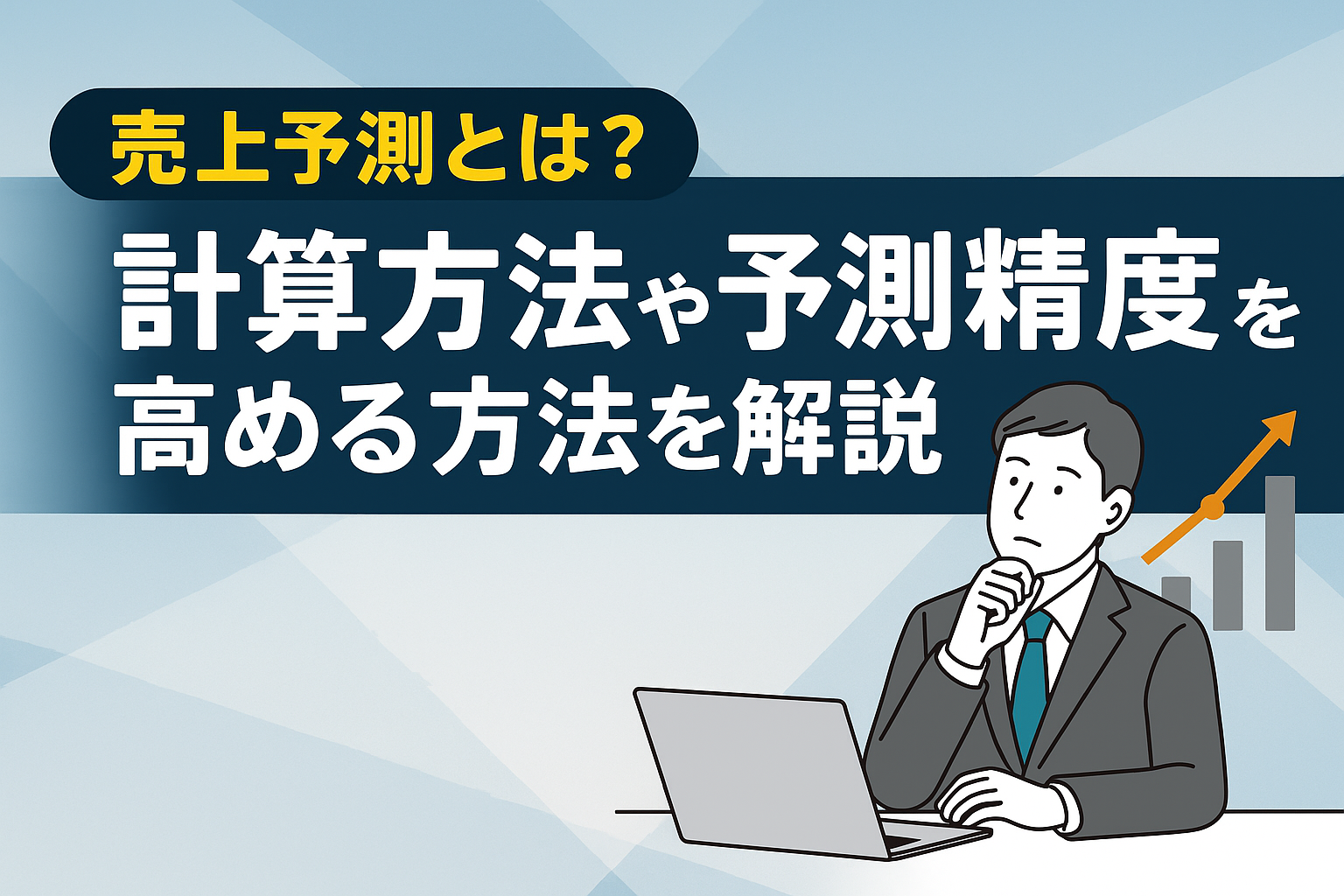
小規模・中小企業の経営者は、人材難や原材料の高騰などの問題を抱えています。中でも、売上不振を問題視している企業の割合が小規模・中小企業全体の3割ほどを占めています。
中小企業庁が公開している2023年10月〜12月の調査データによると、売上不振を問題視している企業の割合が示されています。
- 売上不振を問題としている小企業:34.7%
- 売上不振を問題としている中小企業:28.9%
企業の経営者は、売上不振にならないための売上予測を立てることが重要です。
今回は、売上予測について、計算方法や売上予測の精度を高める方法などを解説します。今後の売上予測を経営戦略の指針に役立てようと考えている企業経営者は、ぜひ参考にしてください。
記事の内容
売上予測とはデータを分析することで今後の売上を予測すること
売上予測とは、あらゆる過去データや現状データを分析して今後の売上を予測することです。売上予測の分析対象には、次の月間・年間データを活用します。
- 期間別の売上
- 商品別の売上
- 顧客別の売上など
売上予測の分析対象となるデータは、期間や商品などそれぞれの項目に絞って調査する必要があります。項目を絞ることで、精度の高い予測数値が期待できるでしょう。
売上予測は、あくまでも予測データです。大まかな計算で算出した場合は実績金額と差異が生じます。実績金額に近い予測数値を求めるには、さまざまな分析対象となるデータが必要です。
また売上予測は売上目標の違いと同じ意味合いに捉えられることもあります。次に売上予測と売上目標の違いを解説します。
売上予測と売上目標の違いは達成目的の違い
売上予測と売上目標の違う点は、達成目的です。
売上予測の達成目的は、将来の売上を統計データを活用して客観的な視点で予測することです。一方の売上目標の場合は、希望的な観測を含めた目標数値の設定ではないでしょうか。
つまり、売上予測は「このような売上実績であってほしい」という目標数値ではありません。経済状況や競合他社の動向もふまえた統計的な予測データの算出になります。
例えば、予測売上の数値は、現在の売上高と1年前の売上高を比較し、今後1年間の売上高見通しなどで活用されます。総務省統計局で公開する統計データでは、産業別の各企業が売上高の見通しとして1年後の売上高の増減予測を行っています。
- 売上が増える
- 売上が変わらない
- 売上が減る
- わからない
これら4つの売上高に対しての増減予測は、希望的な目標ではなく、4年ほど前の売上高の実績数値をもとに統計調査の結果で判断している予測です。要するに、客観的な統計データとして活用できる予測数値と考えられます。
売上予測を立てるメリットは経営戦略の指針となる
売上予測を立てるメリットは、経営戦略の指針となることです。売上予測は、実際の売上データや市場動向データ、経済状況のデータなどの統計データを活用して算出します。そのため、経営戦略の判断指標としても有効です。
売上予測の数値が実績数値により算出されたデータであれば、コスト面の適切な管理にも役立つでしょう。売上予測に合わせたコスト管理は、非効率な投資の抑制効果も期待できます。そのような理由からも、売上予測は経営戦略を立てるうえで重要な参考データになるでしょう。
また、事業計画の立案においても売上予測は重要な経営指標となっています。創業時において、事業計画書を作成する際も「どれだけの売上が見込めるか」という判断指標として売上予測の精度が求められます。
また以下に売上予測を立てるメリットを3つまとめました。
- 人材や資金を適切に配分することで生産性や収益が向上する
- 過剰在庫・在庫不足を防止する在庫管理ができる
- 株主などのステークホルダーに事業計画を共有できる
それぞれ順に解説します。
人材や資金を適切に配分することで生産性や収益が向上する
売上予測は、人材や資金を適切に配分するコストの投資判断に役立つ点がメリットのひとつです。売上が増加したとしても、人材を大量に確保し、設備も充実させていれば当然のことながらコスト面が膨れ上がります。
経営戦略的には、初期投資した莫大なコストを右肩上がりの売上で回収していく場合もあります。ただし、売上予測ではなく、希望的な判断による資金の投入はギャンブル的な要素が高くなるでしょう。つまり、根拠のない売上目標に対して人材や資金を投入することはリスクが高いという判断です。
売上予測は、市場調査や実績データを活用した実現性の高い予測数値を出さなければなりません。市場調査や実績数値による分析データは、客観性と説得力が担保できるからです。
売上予測は、客観性と説得力のある判断指標として活用できます。企業の経営戦略を行ううえでも、経営判断の決定権者を説得するデータになります。人材や資金を配分する精度の高い目安になるでしょう。
そのため、売上予測を立てたうえで行う人材や資金の適切な配分は、生産性や収益の向上が期待できます。
過剰在庫・在庫不足を防止する在庫管理ができる
売上予測を立てるメリットは、過剰在庫や在庫不足などを防止する在庫管理が可能な点です。在庫管理が必要なビジネスでは、「売上に対してどの程度の在庫が必要か」を日々の業務として明確にする必要があります。
過剰在庫は、実際に必要な需要量の在庫以上に入荷してしまった状況です。在庫が多くあるため、売れ残りや保管されたままの在庫がある状態をあらわします。
在庫不足は、手書きで在庫管理を行っている企業などで発生する在庫管理トラブルです。多数・多品目の在庫を扱うビジネスの場合、手書きの在庫管理では担当者の負担が大きくなれば棚卸数量のチェックミスが発生しやすくなります。
また、経営において在庫不足は商品を求めている顧客に商品が提供できない状況を生み出します。戦略的な品薄状態ではなく、単なる管理不足による在庫切れは顧客の購買機会の損失にもつながるでしょう。
経営戦略では、売上予測に応じた在庫管理ができれば、売上指標に対しての在庫数も予測できます。在庫管理が行き届くことで、無駄な在庫が減るため、生産性の向上にもつながります。
株主などのステークホルダーに事業計画を共有できる
売上予測は、自社に出資する株主などのステークホルダーへの投資指標として役立ちます。企業は、株主などのステークホルダーに出資してもらうため、事業計画を立てます。
事業計画は、自社ビジネスの業種業態に適した事業の計画を事業計画書として作成する取り組みです。作成する際は記載内容を明確にしなければなりません。事業計画を明確にする理由のひとつは、自社に投資する株主に対して、つじつまの通った事業内容であることを理解してもらうためです。
事業計画に記載する売上予測は、株主に事業の将来性を判断してもらうための指標になります。事業計画に対して資金支援や協力を得るためには、根拠のある売上予測が必要です。根拠のある売上や収益を予測できれば、有効な投資判断指標として事業計画の共有ができます。
また、事業計画を立てることは、次のメリットにもつながります。
- 経営者の考え方を明文化できる
- 会社の進む方向性を明確化できる
- 会社外部関係者に自社方針を提示できる
- 金融機関からの融資が有利になる
- 将来発生する可能性があるリスク回避に役立つ
これらのメリットが考えられる事業計画は、売上予測のデータにより説得力や実現可能性を高められ、投資判断を促せる共有資料になるでしょう。
売上予測の2種類の立て方や計算方法について解説
売上予測は、2種類の立て方や計算方法があります。2種類の立て方は、次の通りです。
- 過去の売上データから予測を立てる方法
- 現在の営業活動の営業パイプライン
売上予測の2種類の立て方は、それぞれに計算方法があります。具体的に解説しましょう。
過去の売上データから予測を立てる計算方法
過去の売上データから予測を立てる計算方法は、一般的な売上予測の計算方法として活用されています。ただし、過去のデータがなければ予測数値を算出できないため、創業間近の企業には向かない立て方になるでしょう。
過去の売上データから予測を立てる計算式は、次の通りです。
売上予測 = 前年度もしくは過去複数年の売上平均金額 × 事業の成長率
過去の売上データを活用する計算では、事業の成長率を求める必要があります。事業の成長率は、過去複数年の売上実績をもとに計算します。例えば、2年前の売上実績と前年度の売上実績があるとしましょう。
- 2年前の売上実績:800万円
- 前年度の売上実績:1,200万円
1,200万円(前年売上) - 800万円 (2年前の売上)= 400万円(差分)
400万円 (差分)÷ 800万円(前年売上) × 100 = 50%(事業の成長率)
上記の計算式により、過去の売上データを使った売上予測は、次の計算結果となります。
1,200万円(前年売上)× 50%(事業の成長率)= 600万円(売上増加分)
600万円(売上増加分)+ 1,200万円(前年売上)= 1,800万円(当年の売上予測)
過去の売上データを使った計算方法は、あくまでも自社の売上実績のみで判断した予測数値です。より詳細な数値を予測するには、市場動向や経済状況のデータも含める必要があります。
実際の事業資金の融資を目的に作成する経営行動計画書では、5年先の売上高を予測する場合もあります。例えば、中小企業庁が公開する計画書のひな形では、5年先の経営行動計画の売上高の例が記載されています。
- 令和4年売上高:1億7,000万円
- 令和5年売上高:1億7,500万円
- 令和6年売上高:1億8,000万円
- 令和7年売上高:1億8,500万円
- 令和8年売上高:1億9,000万円
- 令和9年売上高:1億9,500万円
計画策定前の売上高1億7,000万円規模の毎年500万円ずつ売上高が増加する傾向で予測を立てています。
売上予測は、このような増加傾向の売上予測について、市場動向や経済状況などを実証する根拠が求められるでしょう。
現在の営業活動も考慮する営業パイプラインから予測を立てる方法
売上予測は、現在の営業活動に考慮した計算方法でも算出できます。現在の営業活動を考慮した売上予測の立て方は、営業フローをパイプライン管理して予測を立てる方法です。
営業パイプラインは、営業活動の成約までのプロセスを細分化・可視化できます。例えば、営業パイプラインで示す営業プロセスでは、次のフェーズで進むことが考えられます。
- 顧客に初回訪問
- 顧客からヒアリング
- 状況に応じた提案
- 見積もり
- 受注
これら営業プロセスのフェーズそれぞれに数値を当てることで営業パイプラインによる売上予測の計算が可能です。計算方法の例として、次の数値を当てはめて算出します。
- 取り扱う商品の価格:100,000円
- 顧客に初回訪問:200件
- 初回訪問で顧客からヒアリングを受ける割合:50%
- ヒアリング後にこちらからの提案に進む割合:60%
- 提案を受けて見積もりに進む割合:50%
- 見積もりから受注につながる割合:70%
これらの数値を次の計算式に当てはめて算出します。
【受注数の予測を算出する計算式】
初回訪問者数 × 各フェーズ通過率 = 受注見込み数
200件 × 0.5 × 0.6 × 0.5 × 0.7 = 21件
【売上予測の計算式】
受注見込み数 × 取り扱う商品の価格 = 売上見込み金額
21件 × 100,000円 = 2,100,000円
例にあげた数値の場合、営業パイプラインによる売上予測は、2,100,000円という結果になりました。このように、営業プロセスの流れに沿って計算する方法もあります。
売上予測の精度を高めて企業の収益を最大化する方法
売上予測は、企業の事業計画を株主などのステークホルダーに共有し、出資や融資などの協力を促すために重要な判断指標です。そのため、重要な判断指標として精度を高める必要があります。
企業の収益を最大化するには、事業の資金調達は欠かせません。売上予測は、出資判断や融資審査の判断指標として根拠になる精度が求められます。
以下に売上予測の精度を高めて企業の収益を最大化する方法についてまとめました。
- 営業担当者全員がコスト意識をもって業務に取り組む
- 予測精度に差が出ないように予測方法を社内で統一する
- 商談データが蓄積できるツールを活用し精度を高める
それぞれ順に解説します。
営業担当者全員がコスト意識をもって業務に取り組む
先述した営業パイプラインの計算方法で考えた場合は、売上予測の精度を高める方法として、営業担当者全員のコスト意識をもつことが必要です。
営業パイプラインの例にあげたプロセスごとのフェーズでは、初回訪問数200件のうち、受注までたどり着くと予測した件数は21件という結果になりました。あくまで例に過ぎませんが、営業担当者は、「200件訪問し最後まで対応できれば21件の受注が期待できる」という目安をもって取り組めます。
営業担当者全員は、営業プロセスのフェーズごとの割合からコスト意識をもって業務に取り組む必要があります。コスト意識をもつことで、非効率な業務を見直し、生産性の高い収益の最大化が期待できるでしょう。
予測精度に差が出ないように予測方法を社内で統一する
売上予測の精度を高める方法は、社内で共有する場合に注意が必要です。予測精度に差が出ないように予測方法を統一しなければなりません。
例えば、営業担当者ごとに予測数値の精度が異なると、売上予測の数値に差が生まれ、資金投入の判断も大まかになります。事業に投入する資金が大まかになると、結果的にゆとりをもったコスト意識につながります。売上予測にブレ幅が生じて、余計な在庫を抱えてしまうことも考えられるでしょう。
社内で売上予測を立てる場合は、予測数値のブレ幅を発生させないために、予測方法の統一が必要です。過去の売上を基準にした計算方法や営業パイプラインで計算する方法など、計算方法は社内で統一しましょう。
商談データが蓄積できるツールを活用し精度を高める
企業の収益を最大化するには、売上予測の精度を高められるツールの活用が必要です。本記事で解説した営業パイプラインの計算方法では、営業プロセスのフェーズごとの結果データによって売上予測が算出できます。
ただし、営業プロセスのフェーズごとにデータを活用する場合は、データ収集や保管、検索、社内連携など活用人数や部署数によって扱いが複雑になります。売上予測を商品別で算出する場合は、複数の商品を扱う事業者だと膨大なデータになるでしょう。
そのような膨大なデータを扱う場合は、営業活動の商談データを蓄積できるツールの活用をおすすめします。商談データを蓄積できるツールは、経営者や中間管理職、営業、事務、デザイナーなどを想定した幅広いユーザーが活用できる商談管理システムの導入が効果的です。
売上予測の精度を高めるなら専用ツール「ジョブマネ」

商談管理システムには、自動で作成した商談データをクラウド上に蓄積し、売上予測の参考データとして活用できるツールがあります。売上予測の精度を高められる専用ツールは、ジョブマネです。
ジョブマネは、自社サーバーやパソコンのストレージに保存するシステムではなく、クラウド上で商談データを管理ができます。クラウド上で管理する仕組みのため、営業担当者は出先からスマホ経由で商談内容を発信できます。
営業担当者が出先で報告した商談内容は、別の場所にいる上司や同僚がリアルタイムで確認できます。つまり、ジョブマネは蓄積された商談データを活用して売上予測を立てた場合、作成や添付送信の手間がなく、鮮度の高い売上予測の共有を実現するツールなのです。
ジョブマネの導入は売上予測の計算において以下のメリットを期待できます。
- データベースを活用した売上予測ができる
- 売上金額が自動で算出されるので手間が省ける
それぞれ順に解説します。
データベースを活用した売上予測ができる
ジョブマネは、プロジェクトごとにグループを作成して連携可能なデータ管理を実現します。プロジェクトごとに蓄積された膨大なデータをクラウド上のデータベースの活用で行います。データベースを活用した売上予測ができる業務管理ツールです。
データベースを活用した売上予測は、すでに蓄積された過去の売上データや商談件数、受注数、期間別(年・月・日など)、商品別に予測数値を算出できます。クラウド上で管理しているため、場所や時間を選ばないチェックが可能です。
売上金額が自動で算出されるので手間が省ける
ジョブマネによる売上予測の計算は、売上金額が自動で算出されるため、予測作業の手間が省けます。表計算ソフトのエクセルなどで売上予測をする際は、異なる部署の売上データなど複数のシート上のデータを連携する作業に手間がかかります。
また、エクセルで作成した予測数値を関係部署に共有する際は、メール添付による回覧が必要な場合もあるでしょう。書類の共有で確認印が必要な社内取り決めがある企業では、算出した売上予測を全社共通認識するまで相応の時間が必要になります。
ジョブマネは、算出した売上予測データなどを含めて業務上のデータはクラウド上に蓄積されます。蓄積されたデータは、時間や場所を問わずツール利用権限のあるユーザーがリアルタイムで確認できる仕組みです。そのため、ジョブマネによる売上予測の算出は、鮮度の高い売上予測をチェックできる仕組みづくりになるでしょう。
鮮度の高さと蓄積されたデータをフルに活用した精度の高い売上予測を求めているのであれば、ジョブマネの導入を検討してはいかがでしょうか。