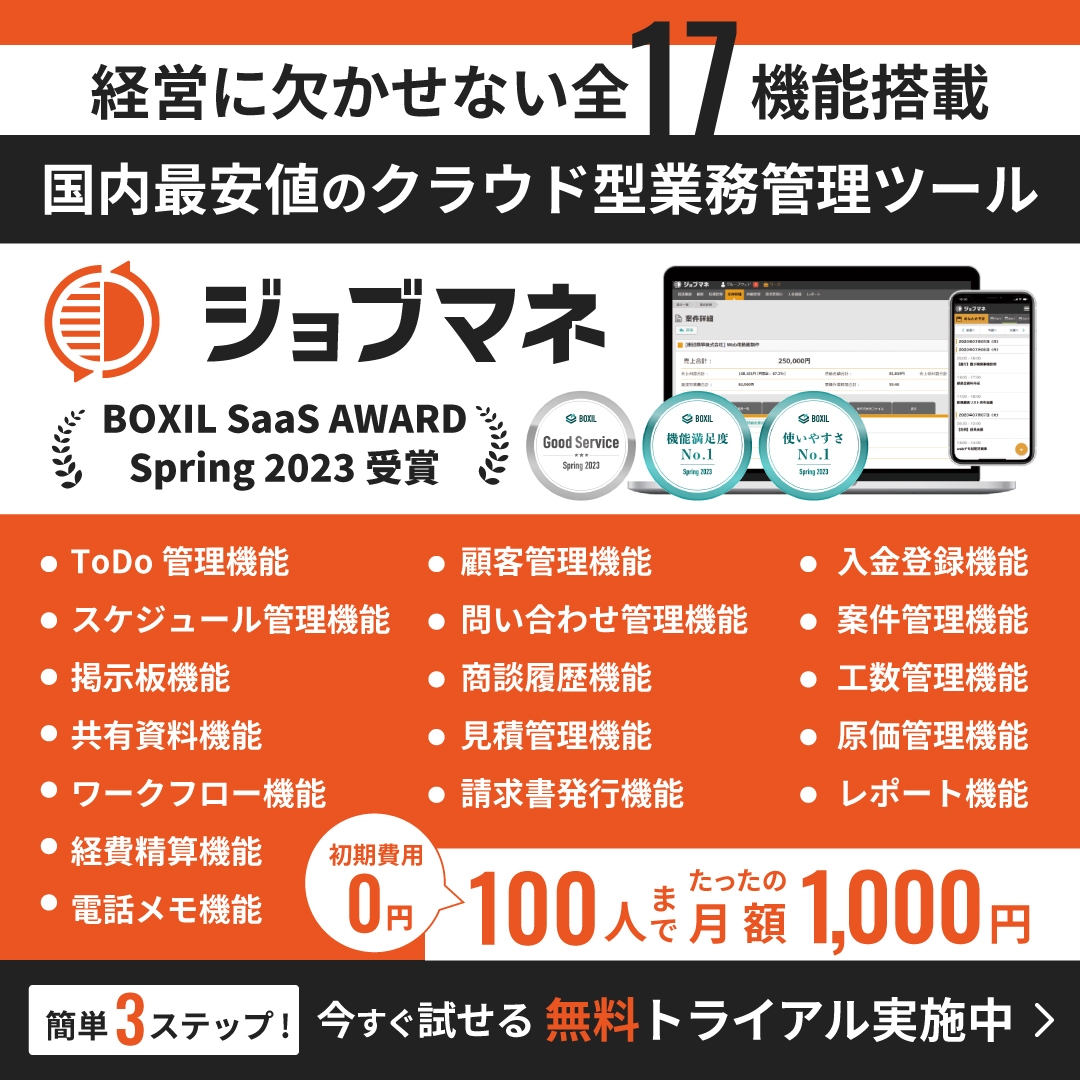属人化とは?デメリットや解消方法を解説!
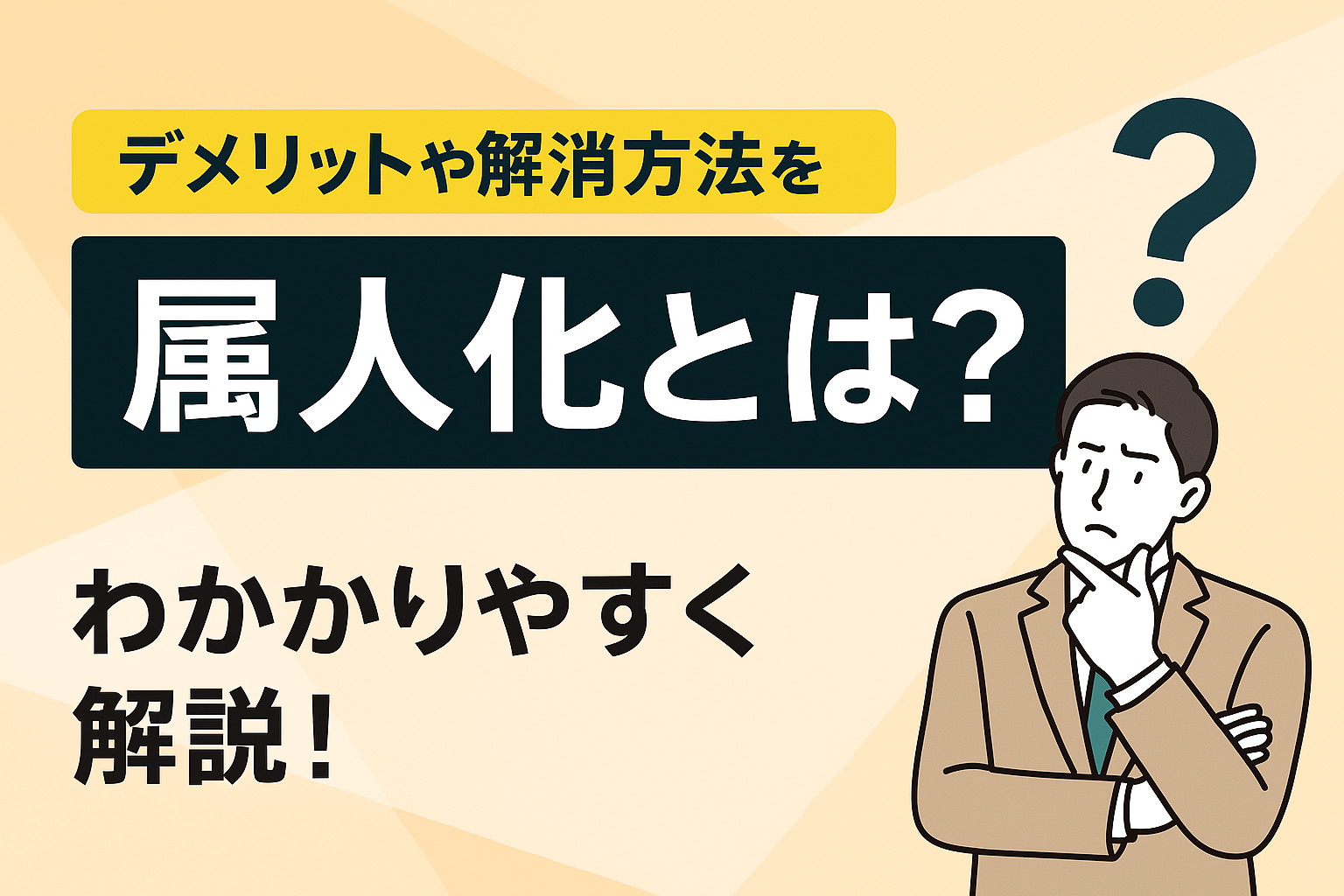
特定近年、多くの企業で「業務の属人化」が課題視されています。特定の担当者しか遂行できない業務がある状態は、組織全体の生産性や業務の安定性を損なう可能性があります。人材の流動性が高まっている現代では、業務が個人のスキルや経験に依存していると、属人化による影響を受けやすくなります。
業務が特定の社員に集中すると技能や経験値も集積されます。業務の効率化が進む側面もあるため見過ごしてしまうのが属人化です。しかし長期的な視点に立つと、業務のブラックボックス化やノウハウ喪失の可能性を含んでいるのです。
本記事では、属人化の原因やデメリットに加え、解消に向けた具体策や有効な業務支援ツールの活用法について紹介します。自社の業務体制を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。
記事の内容
属人化とは組織内で特定担当者に業務依存している状態
企業における「属人化」とは、特定の業務が担当者個人の知識やスキルに強く依存し、他の社員が代替できない状態を指します。
たとえば、その担当者しか業務手順やノウハウを理解していない状況や、適切な引き継ぎマニュアルが存在しない状況を指します。
一方で特定の業務に対して深い知識やノウハウを持つ社員や、手順を熟知している社員がいることで、業務がスムーズに進行し、生産性も上昇するケースがあります。また、状況に応じた判断が求められる場面においても、特定業務の「専門家」として担当できるため、業務の属人化がむしろ強みとして機能するケースもあります。
ただし、これらの側面は短期的な視点や安定した環境の中で成立するものであり、長期的に見ると組織の柔軟性や持続性を損なうリスクが高まる点に注意が必要です。
属人化が進むと、業務がブラックボックス化し、担当者が不在になった際に業務が停滞するリスクが高まります。短期的には業務効率や品質を維持できる場合もありますが、長期的にはノウハウの共有がされず、組織全体の成長や人材育成が妨げられる懸念を抱えているのです。
そのため、属人化のメリットを活かしつつ、組織としては業務の標準化・共有・バックアップ体制の整備を並行して進めていくことが重要です。チームとして業務を支える仕組みづくりを重視しましょう。
属人化を防ぐためには業務の標準化が重要です。業務の標準化とは、業務の手順やルール、判断基準を明文化して、一定の手順で遂行することにより業務の品質を保つ仕組みを指します。効率的かつミスの少ない標準的な手順を整備するため、人を問わず同様の成果が得られます。
また、業務の標準化の推進により業務内容のムリ・ムダ・ムラが明確になり、教育コストの削減や業務改善などのメリットにもつながります。
業務の属人化が発生する主な原因について解説
属人化が発生する主な原因には、担当業務の固定化、業務マニュアルの不備、教育リソースの不足などが挙げられます。
まず、特定の担当者が長期間にわたって業務を担うことで専門性が高まり、業務のクオリティが安定しやすくなる一方で、他の社員が関与しづらくなる状況が生まれます。
また、業務マニュアルが存在しない、あるいは内容が古くて実態と合っていない場合は、引き継ぎが非常に難しくなります。日々の業務に追われる現場では後進育成や情報共有が後回しにされがちです。
特定の人が業務を回せる状態が組織として助けになることもあるため、気づかないうちに属人化が進行します。短期的に見ると重宝する属人化ですが、長期的な企業運営の視点では一定のリスクとなります。まずは組織全体で業務の可視化と標準化を進める意識改革が必要です。
以下に属人化が発生する原因について具体的にまとめました。
- 業務マニュアルが十分に整備されていない。
- 特定の担当者が継続して業務を行うことで専門性が高まる
- 業務負担が大きいと教育に割く余裕がなくなる
それぞれ順に解説します。
業務マニュアルが十分に整備されていない
業務マニュアルの未整備は、属人化が進行する根本的な要因の一つです。
マニュアルが存在しない、あるいは形骸化していて実態と乖離している場合、業務の手順や判断基準が担当者の頭の中にしかない状態に陥ります。そのため、他のメンバーが業務を再現することが困難となり、業務が特定の人物に固定されてしまいます。
ここでマニュアルの存在にも注意が必要です。マニュアルが存在していても内容が更新されず、不十分であれば存在の意味がありません。古いマニュアルが現場の混乱を招く可能性もあり、異動時の引き継ぎや代替要員の教育も非効率となります。
属人化を防いでスムーズに後進人材を教育するには、定期的な業務プロセスの見直しとマニュアルの更新、誰でも再現できる業務フローの構築が重要です。
特定の担当者が継続して業務を行うことで専門性が高まる
同じ担当者が長期間にわたって業務を担うことで、自然とその業務に関する深い専門性が身につきます。
これは組織にとって一種の強みですが、同時に他の社員が業務に介入しづらくなるという弊害も発生します。特定の担当者が業務の知識や手順を集中して担う形になれば、他メンバーとのスキルや情報に格差が生じ、さらなる属人化や依存状態が進みます。
このような状況では、担当者が休職・退職した際に代替者がスムーズに業務を引き継げないという重大なリスクを抱えています。リスクに対処するには、業務ローテーションやペアワークの導入など、業務知識の分散と共有を進める体制づくりが重要です。
業務負担が大きいと教育に割く余裕がなくなる
業務量が多くなると、誰しも目の前の作業をこなすことで精一杯になりがちです。その結果、後進の育成やノウハウ共有が後回しにされていきます。
とくに繁忙期などでは教育や引き継ぎが業務の優先順位から外れてしまい、担当者が一人で業務を抱え込んでしまいます。このような状況になると、ベテランの担当者だけが業務を引き受けることになり、人員の代替が非常に厳しくなります。
この問題を解決するには、組織として意識的に教育や引き継ぎの時間を確保し、定期的に業務負荷の調整や人員配置の見直しを行うことが重要です。
繁忙期の前に引き継ぎスケジュールを組んでおく、人材教育に対応できるよう一時的にでも増員する、人員配置の時期をずらす、などの工夫も想定されます。「忙しいから教育できない」を常態化させないための制度設計が求められます。
業務の属人化が引き起こす3つのデメリット
業務の属人化が進行すると、企業が抱えていた多様な問題が表面化します。第一に、担当者が不在の際に業務が滞るリスクの高まりです。
また、業務の内容が外から見えづらくなるため、客観的な人事評価が困難になるという問題も発生します。どれだけの業務をこなしているかが可視化されなければ、適正な報酬や評価に反映されず、社員のモチベーションの低下を招く可能性があります。
さらに深刻なのは、業務に関する知識やノウハウが組織に蓄積されないまま、担当者の離職とともに重要な情報が失われてしまうリスクです。
厚生労働省が公開している「働き方改革」に関する資料(「働き方改革」実践の手引き)においても、業務の属人化が専門分野における少人数への業務集中、長時間労働の一因として指摘されています。
とくに、若手の育成不足や特定社員への過度な業務集中が企業全体の構造的課題であり、業務の過集中とともに長時間労働や離職につながる要因として分析されています。
また以下に業務の属人化が引き起こす3つのデメリットについてまとめました。
- 業務担当者不在による業務の遅延や停滞の可能性
- 業務内容の把握が困難になるため適切な人事評価を下しにくい
- 業務担当者の不在や退職によるノウハウの喪失
それぞれ順に解説します。
業務担当者不在による業務の遅延や停滞の可能性
業務の属人化が進むと、業務担当者が不在の場合に業務の遅延や停滞が起きるリスクが高まります。
担当者の体調不良や突然の退職があった場合、他の社員が業務の詳細を把握しておらず、すぐに引き継ぐことが困難です。その結果、納期の遅延や取引先との信頼関係に影響を及ぼす恐れがあります。
とくに、業務手順が明文化されず、暗黙的なノウハウや個人の知識・経験に頼って業務を進めているケースでは、その担当者がいなくなれば業務はすぐに停滞します。スケジュールの遅延や信用低下に直結する恐れがあるのです。
このように、特定の担当者に依存する業務体制では組織全体の安定性が損なわれやすく、突発的な事態への対応力も弱くなります。業務の属人化を回避するには、業務の標準化やマニュアル整備を進め、複数人が対応できる体制を整備することが不可欠です。
業務内容の把握が困難になるため適切な人事評価を下しにくい
特定の業務での属人化が進むと、業務の進行状況や難易度、実際の貢献度が周囲から見えにくくなります。特定の人物に知識や技能が集中していると、業務負担への理解が生まれず、業務の成果やプロセスが上司や評価者に十分に伝わりません。
実際の努力や貢献が正当に評価されない可能性があり、公正な人事評価が行われないまま不公平感だけが生じます。結果として、特定の業務を負担してきた人材が流出する事態になりかねません。引き継ぎの難しい業務の担当者が離職すると、それだけで業務の中断や遅延につながります。
このような業務の中断や引き継ぎの混乱を防ぐには、評価制度の透明化とともに、少なくとも上席による業務内容の把握が必要です。専門的な業務であってもその業務内容を可視化し、上席をはじめ、企業全体で業務の流れや重要性を明確にする体制の構築が求められます。
業務担当者の休職や退職によるノウハウの喪失
業務の属人化の最大のリスクといえるのが、担当者の休職や退職によって、これまで蓄積されたノウハウが一気に失われてしまうことです。担当者しか知らない業務プロセスや判断基準が共有されていなければ、後任者への引き継ぎは非常に困難となり、再構築には多大な労力と時間を要します。
また、ノウハウが失われることで業務品質が一時的に大きく低下し、企業の競争力にも悪影響を及ぼす恐れがあります。さらに、新たな人材を育成するには時間とコストがかかり、その間の業務停滞が企業全体に与える影響は少なくありません。
このような事態を防ぐには、日頃から業務プロセスや知識を組織内で共有し、定期的に見直す体制の構築が重要です。業務マニュアルの整備、ナレッジの共有、定期的な研修や教育などの取り組みを通じて、誰が担当しても同じレベルで業務を遂行できる環境を整えましょう。
業務の属人化を解消するための3つの方法
業務の属人化は、一般的に組織の効率や柔軟性を損なう要因であるとともに、目の前の業務だけを見れば特定の人材がパフォーマンスに優れている状況でもあります。企業としては手放しがたい現状かもしれません。
しかし、業務全体の最適化の観点としては大きな懸念が存在します。業務の見える化と情報・ノウハウの共有を進め、依存状態から脱却すべき状態です。業務の「見える化」と「情報やノウハウの共有」を進め、チーム全体としてのパフォーマンス向上を図りましょう。
業務の属人化を解消する具体的な方法は以下の3つです。
- 業務内容を整理してマニュアル化や標準化を進める
- 進捗確認や担当業務の明確化のために対話の頻度を増やす
- チーム全体で情報共有できる仕組みを整える
それぞれ順に解説します。
業務内容を整理してマニュアル化や標準化を進める
属人化を防止するうえで基本的かつ重要なのが、業務内容の整理と標準化です。業務手順を明確に記したマニュアルやチェックリストの作成により、誰でも同じように業務を実行できる仕組みを整備できます。
特定の担当者に偏っている業務、他の代替が難しい業務については、多くの場合、その担当者が知識や経験を集積し、独自の手法で進めているケースがあります。そのままだと他のメンバーが引き継ぎしにくい状況です。これらの重要な手順や判断基準を詳細に明文化することで、担当者が変更になっても業務品質を一定に保てます。
マニュアルの整備によりノウハウや知識が組織に蓄積され、担当者が変わっても同様の手順で業務が遂行されるため、業績の安定にもつながります。これまでに培ってきた経験・感覚・反省点を明文化できれば、新人教育や異動時の引き継ぎもスムーズになるでしょう。
進捗確認や担当業務の明確化のために対話の頻度を増やす
業務の属人化の解消には、企業内でコミュニケーションの頻度を高め、業務の進捗や役割を明確にする環境を整えましょう。
定期的なミーティングや朝礼、週次報告の場を設けることで、業務状況や進捗を可視化できます。特定の担当者に業務が集中している場合には、このような対話を継続することで他のメンバーが業務の一部を担えるような調整や、業務負荷の分散が可能になります。
また、対話の機会を増やすことで困りごとや課題が発生した際も早い段階で共有が可能です。トラブル回避や迅速な対応が期待できます。継続的な対話は業務の理解を深め、突発的な不在にも対応しやすい体制を作るうえで重要な要素です。
各担当者の業務を見える化し、周囲が支援しやすい環境を整えることで、属人化の防止と協力体制の構築にもつながります。定期的な報告と確認を習慣的に実施する企業風土を醸成し、特定の人材に過度に依存しすぎない体制を構築しましょう。
チーム全体で情報共有できる仕組みを整える
情報共有の体制を整えることにより、業務の引き継ぎや代理対応が格段にスムーズになります。業務に関する情報や資料、ノウハウが誰でも簡単に確認・活用できる状態にしておくことで、特定の人にだけ情報が集中する状況を回避可能です。
具体的には、クラウド型のファイル共有サービスやタスク管理ツールなどを導入する方法で、業務の進捗や作業内容をチーム全体で常に把握できるようになります。さらに、ナレッジベースや社内の業務手順・ノウハウ集を構築し、担当者の持つ知見を定期的に文章化して蓄積しておくと、上席や他のメンバーが速やかに対応できます。
このような情報共有の仕組みが根付くことで、メンバー間の知識やスキルの偏りが緩和され、誰が担当しても一定水準の成果が出せる環境が整います。その結果、属人化が抑制され、全体の業務効率や生産性の向上が実現します。
属人化を解消するなら専用ツール「ジョブマネ」の導入がおすすめ

業務の属人化を根本から解決するには、業務支援ツールの活用が非常に有効です。
なかでも「ジョブマネ」は業務の標準化と可視化に優れたクラウド型ツールとして、多くの企業で導入が進んでいます。ジョブマネのワークフロー機能を活用すれば、各業務の進行状況を一目で把握でき、担当の割り振りや対応状況が明確になります。
業務支援ツールで業務を管理することで、タスクの遅れや停滞が発生している部分もすぐに特定できるため、適切なタイミングでのフォローアップも行いやすくなります。
さらに、ジョブマネに搭載されているファイル共有機能により、チーム内での情報共有をスムーズに実現します。業務に関するドキュメントやノウハウを一元管理することで情報の属人化を防ぎ、教育や引き継ぎの効率化にもつながります。
ジョブマネは属人化を解消し、チーム全体の生産性を底上げする有力な支援ツールとなるでしょう。
以下に属人化の解消に役立つ機能をまとめました。
- ワークフロー機能で業務の進捗状況が一目でわかる
- ファイル共有システムで情報共有がスムーズになる
それぞれ順に解説します。
ワークフロー機能で業務の進捗状況が一目でわかる
ジョブマネに搭載されているワークフロー機能を使えば、業務の進捗がリアルタイムで確認できます。業務フローをステップごとに管理でき、作業が完了すると自動的に次の担当者へ通知されます。業務の停滞や抜け漏れを防ぎ、担当者の負担を分散。結果として業務負担の集中を防ぎ、進捗管理が容易になります。
タスクは期限付きで設定できるため、誰が何をいつまでに対応するのかが明確になり、記録も残ります。その結果、担当の重複や認識のずれが起こりにくくなり、進捗管理がスムーズになります。チーム内での連携も強化され、業務の透明性と効率が向上します。
ファイル共有システムで情報共有がスムーズになる
ジョブマネには高性能なファイル共有システムが備わっており、業務に必要な情報や資料をクラウド上で一元的に管理できます。柔軟な権限設定により、必要な人だけが閲覧・編集できるような制御も可能です。これにより、安全かつ効率的に情報を共有できます。
さらに、ジョブマネでは日報や週報などの報告機能も用意されており、定期的な業務報告を通じて業務の偏りを防止します。
コミュニケーション機能を使って業務の相談や確認をその場で行えるため、情報の共有や意思疎通がスムーズになります。チーム全体で業務を把握できる環境が整うため、業務の属人化を根本から防ぐ体制づくりが可能です。
ジョブマネの機能
①工数管理機能
各メンバーの業務にかかった時間を正確に記録・集計。誰がどの業務にどれだけの時間を要しているかが明確になり、適正な人員配置や業務配分を実施できます。人員配置や業務改善のための客観的なデータを取得可能です。
②SFA(営業支援)機能
ジョブマネの営業支援機能は営業プロセスを可視化し、各営業担当の活動や進捗状況をリアルタイムで管理できます。商談の進捗管理や売上見込み予測なども簡単に行えるため、戦略的な営業活動が可能です。組織的な営業力を強化し、成果向上につなげます。
③顧客管理(CRM)機能
取引先情報や過去の商談履歴、対応内容などを一元的に管理でき、過去の取引履歴や顧客とのやり取りを参照可能です。営業やサポート活動の精度を高め、顧客満足度の向上や営業力の強化をサポートします。
④プロジェクト収支管理機能
売上や経費の記録から収益性や進捗状況を自動で算出。プロジェクトごとの採算性をリアルタイムで把握でき、不採算プロジェクトの早期発見や迅速な改善策の実施が可能です。
⑤経費精算・承認フロー機能
交通費や立替経費などの精算申請や承認をジョブマネ上で管理できます。スマートフォンからの申請や承認も可能なため、大幅な時短に貢献。申請から承認までのフローも明確化されるため、精算業務の効率化と透明性向上につながります。
⑥見積書・請求書の発行機能
過去の取引データから見積書や請求書を作成・保管。作成した見積書や請求書はクラウド上で保管され、紙ベースでのやりとりを削減します。事務処理の効率化と正確性の向上につながります。
ジョブマネの導入により、業務の可視化と情報共有が一気に進みます。全員が業務の流れを把握できるようになり、ノウハウやデータを一元管理することで業務の知識が組織に蓄積されます。
情報共有と組織全体での連携が強化され、属人化の防止だけでなく、チーム全体の連携力や業務効率も高まり、持続可能な業務体制が構築されます。また、クラウド型のため、リモートワーク環境でもスムーズな情報共有や業務管理が可能です。