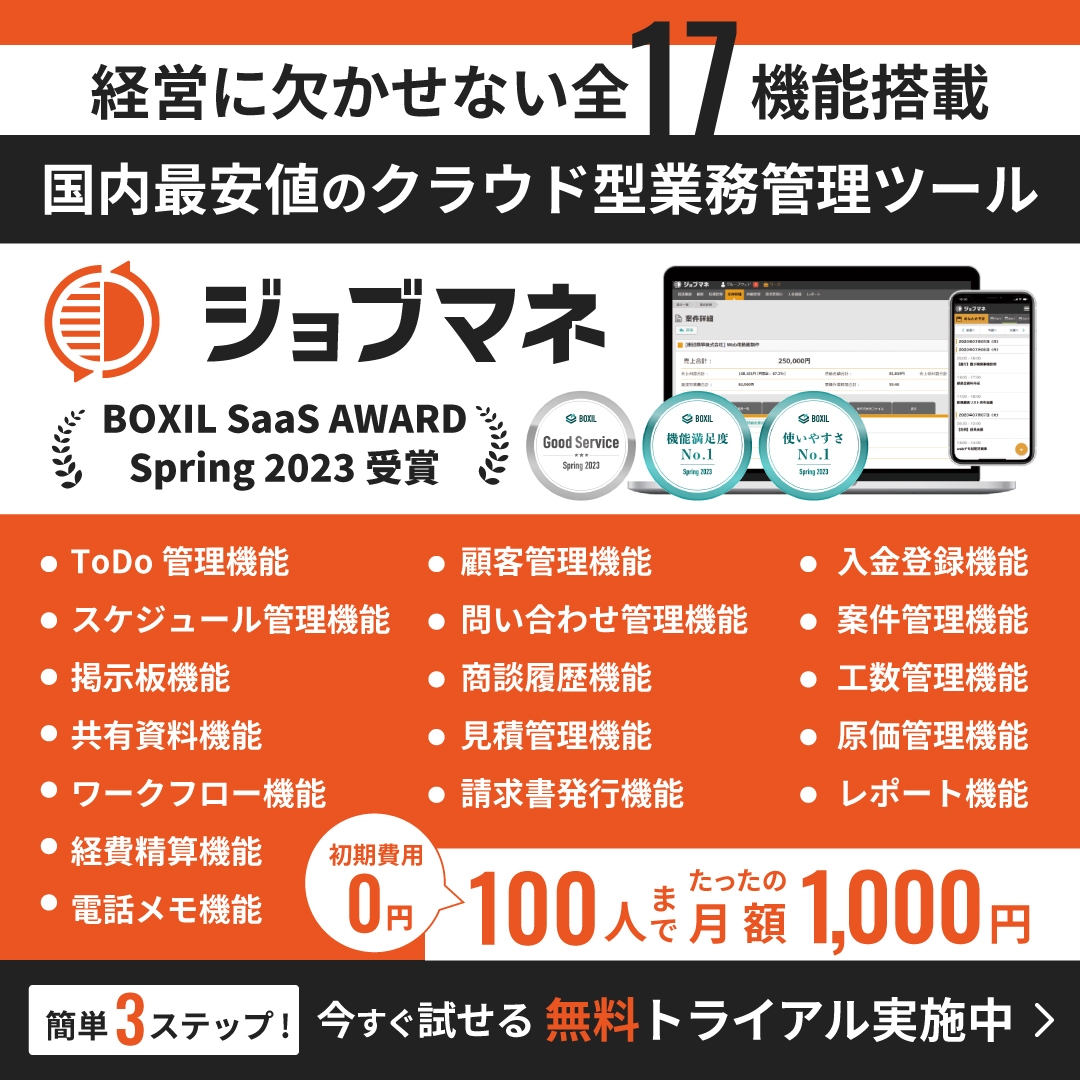稟議書のテンプレート・例文一覧!承認される書き方とは?
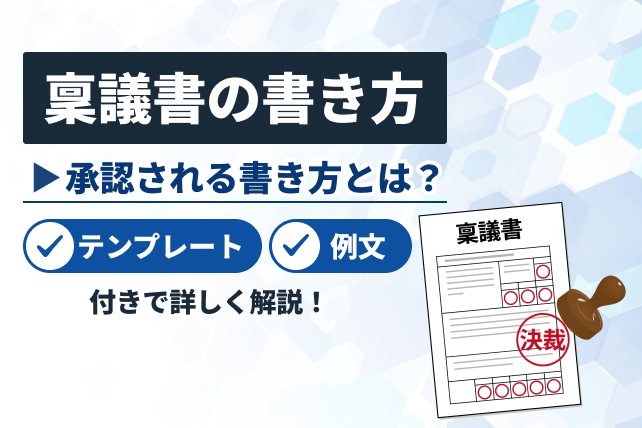
会社では、物品の購入や人事異動、新規契約など担当社員が判断できない意思決定は、上司の承認が必要になるでしょう。稟議は、会社組織における経費の発生する事項に対して上司の承認を得る手続きです。一般的に稟議の手続きには、稟議書を作成します。
稟議書は、申請する内容に沿った項目などの書き方が異なります。「どのように書いたら良いのか」と迷っている場合は、申請する内容に適した稟議書テンプレートの利用が役に立つでしょう。
稟議書のテンプレートは、項目や例文などがあらかじめ記載されています。本記事では、稟議書のテンプレート一覧を紹介します。また、承認される稟議書の書き方などもあわせて解説するので、稟議書の書き方で困っている担当者は、ぜひ参考にしてください。
記事の内容
稟議書とは経費が発生する業務に対して上司から承認を得る文書
稟議書は、担当社員のみで判断できない業務に対して上司から承認を得るための文書です。
会社では、稟議書を回す承認フローがさまざまな場面で発生します。例えば、以下の場面です。
- 新規契約において条件の変更を求められた際の承認
- 外部企業との取引において提示された発注金額に対しての承認
- 新規プロジェクトの立ち上げで導入するタブレット端末の購入に対しての承認
- 遠方の取引先の設備環境を現地調査するための出張費発生に対しての承認
- 部署間の人事異動を承認など
- 外部研修・セミナーへの参加に伴う受講費用・交通費の発生に対しての承認
会社において承認作業が発生する業務は多岐にわたるため、稟議書の作成は日常の業務に欠かせない取り組みになります。
会社の業務規定の範囲内であれば、稟議書を書く状況は訪れないかもしれません。しかし、規定で定めている以外の事象が発生した場合や、想定外の経費が発生する場合は担当部署の上司の承認が求められます。その際に必要となる文書が稟議書です。
また以下に稟議の流れや決裁書・起案書との違いをまとめました。
- 稟議は起案から始まり回付・承認を経て最終的に決裁される
- 稟議書と決裁書の違いは最終承認を証明する文書かどうか
- 稟議書と起案書の違いは意思決定に必要な提案文書かどうか
それぞれ順に解説します。
稟議は起案から始まり回付・承認を経て最終的に決裁される
稟議とは、企業や組織が新しく物事を進めるにあたって上司や担当部署などの承認を得るための手続きです。
会社は、従業員が新規事業の企画を立てた場合やその企画に必要な経費などを申請する場合に組織内で「実行するか却下するか」を判断しなければなりません。
稟議は、「従業員の企画や申請に対して、組織内で意思決定を行う重要な業務」とも判断されています。
会社組織に稟議の手続きがない場合は、従業員が勝手に企画を進めて経費も使う状況が考えられます。稟議の手続きがない状況では、会社の経営は成り立ちません。そのため、規定に定められていない内容による変更がある場合は、事象の大小に関係なく稟議が必要になるでしょう。稟議が必要になる状況では、必ず起案者が存在します。
例えば、新規事業の案件(起案)に対して、人員の増強が必要になったり、設備投資が必要になったりすることが考えられます。そのような状況では、新規事業を進めるにあたって「必要な経費として会社に認めてもらいたい」と承認を得なければなりません。
承認を得るには、稟議の流れを理解する必要があります。稟議を申請して承認されるまでの流れは、以下の通りです。
- 起案:稟議の対象となる事項を企画・提案する
- 回付:稟議内容に関係する担当部署や決裁者への文書回覧
- 承認:各関係部署の承認を得る
- 決裁:決裁権者による最終承認を得る
このように、稟議は起案から始まり、その案を関係部署に回付・承認を得て最終的に決裁されるように進めます。稟議書は、承認のうえ最終的に決裁されることを目的に書く書類です。
稟議書と決裁書の違いは最終承認を証明する文書かどうか
稟議書と決裁書は、目指す目的が決裁という部分では同じ内容と思われるかもしれません。
しかし、稟議書と決裁書には、次のような違いがあります。
- 稟議書:上長の承認を得る目的で作成する文書
- 決裁書:上長の最終承認を証明する文書
稟議書の作成は、稟議する事項を起案した担当者が行います。
一方の決裁書は、稟議を受けた決裁権者が最終的に承認したことを証明する文書です。そのため、稟議書と決裁書では、書面の効力を生かす場面が異なります。
例えば、稟議書は承認してもらいたい事項に対して上長の納得を得るためのデータや事実確認などを記載します。一方の決裁書は上長からの承認を受けたことを関係者に認めてもらうための証明書類です。つまり、稟議書と決裁書は書類として効力を生かす対象が異なります。
また、稟議書と決裁書では使用するタイミングも異なります。稟議書は、関係部署や上長などの承認を求める初期段階から中期段階に必要な書類です。一方の決裁書は申請した稟議が承認されたあとに発行されます。
要するに、稟議書と決裁書では、効力を生かす対象と使用するタイミングに違いがあると言えるでしょう。
稟議書と起案書の違いは意思決定に必要な提案文書かどうか
稟議書と起案書は、使う意味や役割に違いがあります。
前述した稟議の流れで説明した通り、稟議は起案から始まります。そのため、起案書は稟議のプロセスにおける一部「起案」の段階で提出する書類と考えられるでしょう。稟議書と起案書は、使う場面において次の違いがあります。
- 稟議書:起案した内容を関係部署や決裁権者に承認してもらうための文書
- 起案書:稟議内容(企画や提案)を具体的にまとめた文書
このように、稟議書の作成にあたり、起案内容を具体的にまとめた書類が起案書と判断する場合もあるでしょう。ところが、公的機関では起案書と稟議書を同じ意味で使っているケースもあります。
教育現場では、「起案書は、起案者と協議者、決裁にいたる組織的対応のいきさつを明らかにするための書類」と定義して使っているケースもあります。稟議書ではなく、起案書が稟議の承認プロセス全体を担う形式で使われているケースです。
北海道総務部人事局人事課の公開している文書の起案では、行政機関としての「起案」の意味について「起案とは行政期間が収受した文書または自らの発意に基づき、行政機関としての意思を決定するための案文を作成すること」と定義しています。
行政機関の定義を参考にした場合は、起案書は、意思決定に必要な提案を書いた文書と考えられます。稟議書は、起案書も含めた承認までのプロセスに必要な文書と言えるでしょう。
稟議書を書くメリット・デメリットと必要性について解説
稟議書は、書くにあたってメリットとデメリットが考えられます。稟議書の必要性は、稟議の意味として上長や関係者の承認を得る点にあります。会社組織によっては、稟議書を書くことでそれら関係者の理解を得られるメリットと、理解を得るまでの手間がかかるデメリットなどが考えられるでしょう。
また以下に稟議書作成におけるメリットとデメリットをまとめました。
- メリットは会議の手間を省けることや承認者を明確にできること
- デメリットは稟議書の作成や最終承認までに時間がかかること
それぞれ順に解説します。
メリットは会議の手間を省けることや承認者を明確にできること
稟議書のメリットは、会議の手間を省けることです。稟議書を作成しないで会社運営を進めた場合は、何か新しい取り組みや変更・修正などの提案があるたびに会議を開かなければなりません。
少人数で運営している組織であれば、毎朝の定例の打ち合わせなどで決裁権者など関係者が参加する会議を開催できる場合もあります。しかし、組織の規模が大きくなった場合は決裁権者や関係部署の担当者などが常に参加する会議を開くことは困難です。
コロナ禍以降最近では、テレワークを導入している企業も増えてきました。総務省の調べによると、コロナ前の2019年にテレワークを導入している企業は全体の20.2%だった状況から次のように推移しています。
- 2020年:全体の47.5%
- 2021年:全体の51.9%
- 2022年:全体の51.7%
- 2023年:全体の49.9%
テレワークが日常化している企業では、オンライン会議などの開催も考えられます。ただし、提案事項の意思決定のたびに会議を開く必要があり、効率性を目指したテレワークでも会議開催の手間がかかるでしょう。
稟議書は、提案する内容を客観的に判断してもらう目的で書く文書です。そのため、文書の回覧により会議の開催を不要とする役割をもっています。
また、稟議書に記載事項を記録することで、承認者を明確にできます。
デメリットは稟議書の作成や最終承認までに時間がかかること
稟議書のデメリットは、作成や最終承認まで時間を要することではないでしょうか。
大企業のように、決裁権者が多ければ最終承認までの時間がかかることが考えられます。
総務省の見解では、企業の現況では、社内稟議の際に紙の様式が必要になるため、オンライン経由での回付や承認の効率性を実現しにくい状況と判断しています。
稟議書を紙で回付した場合は、回付者の人数や承認数次第で最終承認までの時間がかかるでしょう。稟議書の承認プロセスを紙で行っている企業は、迅速な稟議承認が難しい状況と考えられます。
そのため、起案者は稟議書を書く時間だけではなく、その後の回付や最終承認までの時間も含めて予定を立てなければなりません。もしくは、稟議書の紙ベースの回付を見直す必要があります。
稟議書は会社側のメリットを明記したものが承認されやすい
承認がおりる稟議書に共通している点は、会社側のメリットを明記してあるかではないでしょうか。
稟議書は、自社の利益につながる提案を実現するために作成します。会社にとって利益につながらなければ、経費をかけるだけ無駄になるかもしれません。
承認がおりる稟議書は、会社にとってのメリットを明記することを前提に作成しましょう。
その点を踏まえて、以下に稟議書の書き方のポイントをまとめました。
- 事前に調査を行いデータや事実に基づいた根拠のある稟議書を書く
- 承認前に口頭で内容を説明し必要に応じて稟議内容を見直す
- 会社にとって利益やメリットにつながることを具体的に示す
それぞれ順に解説します。
事前に調査を行いデータや事実に基づいた根拠のある稟議書を書く
稟議書に記載する内容は、正しくなければなりません。正確なデータや事実に基づいた内容でなければ決裁権者の承認は得られないでしょう。
例えば、人事異動の稟議書を作成する場合、決裁権者は、その人事異動が「会社にとってどのような利益を生むか」という点を判断します。
もし、人事異動の稟議において、「過去に同じ部署で働いていたため」や「気心を許せる人物なので」など、起案者の主観的な事情だけの提案であれば、承認は得られないでしょう。
稟議書を作成して承認を得るには、回議者や決裁権者が客観的な立場で判断しても納得のいく内容が求められます。客観的な納得を促すには、事前の調査による正確なデータや事実に基づいた根拠が必要です。
先ほどの人事異動の例にあてはめると、「異動先の部署にITに情通した人材がいないため」や「現在進行中のプロジェクトにITスキルが求められるため」、「異動元の部署には他にITスキルの高い人材が複数名在籍しているため」など、人事異動に対してメリットになる部分を明記します。
さらに、事前調査において現在の異動元の部署の業績や異動先の部署の課題、異動対象の人材の実績やスキルなど、定量的な数値データにより稟議書に記載できれば根拠として説得力が高くなります。承認がおりるための稟議書は、客観的で理解しやすい根拠のある書き方を意識しましょう。
承認前に口頭で内容を説明し必要に応じて稟議内容を見直す
承認がおりる稟議書は、書くだけでは伝わらない場合もあります。起案者は、決裁者が承認する前に口頭で内容を説明しておくことも必要です。
稟議書は、目を通した相手を納得させる目的で書きます。ただし、場合によっては口頭で説明することも必要かもしれません。新規事業の提案では、組織に関わる全部署の同意を得られるかは不透明です。ある部署にとってはメリットにつながるが既存の部署にとってはデメリットになる場合もあるでしょう。
例えば、デジタルツール導入の承認を得る際は、業務効率化に向けた取り組みとして作業時間の大幅なコストカットを訴求できます。
しかし、一方で人件費カットを危惧した既存社員から反発される可能性もあります。
このような場合は、すべてを稟議書に記載するのではなく、状況に応じた対応が求められるでしょう。決裁権者が承認する前に、稟議書に記載していない部分について、口頭で説明する必要があります。決裁権者への説明に対して必要であれば稟議内容を見直せます。要するに、稟議書は状況に応じて臨機応変の対応も考えておきましょう。
会社にとって利益やメリットにつながることを具体的に示す
稟議書を書く際は、会社にとって「どんな利益があるのか」「どんなメリットがあるのか」などを具体的に示しましょう。会社にとっての利益を具体的に示す方法は、原価を下げて利益を増やすか、そのままの原価で価格を上げて利益を増やすしかありません。
価格アップと原価ダウンは、会社の利益を増やすために必要な施策ですが、取り組み方によっては一時的な成果となってしまう危険性もあります。
- 価格アップ→競争力の低下
- 原価ダウン→製品の品質やサービスなどの低下
これらにつながれば、事業は顧客や自社人材が離れてしまう要因にもなるでしょう。会社にとって利益やメリットにつながることは、マイナス要因も含めて考えることが大事です。
取引先との交渉やIT導入など、周囲の反応を見ながら具体的な提案を示しましょう。稟議書に書く際は、関係部署すべてに伝わる具体性を目指して作成することをおすすめします。
稟議書のテンプレート・例文一覧!5W2Hを意識しよう
稟議書には、状況に応じて使い分けられるテンプレートがあります。ここでは、稟議書のテンプレートを例文も含めて一覧で紹介します。
稟議書には、「こう書かなければならない」という決まりは存在しません。決まりではなく、稟議の目的に適した文書の作成が求められます。書く際のポイントは、「5W2H」を意識することです。
【5W】
- Who:誰が
- What:何を
- When:いつ
- Where:どこで
- Why:どのような理由で
【2H】
- How:どのような方法で
- How much:いくらで
稟議書は、5W2Hを意識して書くことで、目的や理由に具体性をもたらします。そのうえで稟議書テンプレートを使う際は、目的に適した記載事項の書かれたテンプレートを選びましょう。
以下に目的別のテンプレートをまとめました。
- 物品購入の稟議書は必要性・緊急性・効果を明記しよう
- 新規取引先との契約締結の稟議書は妥当性を明記しよう
- システム導入の稟議書は導入目的や期待される効果を明記する
それぞれ順に解説します。
物品購入の稟議書は必要性・緊急性・効果を明記しよう
物品購入の承認を得る場合は、その物品の必要性や緊急性、効果などを具体的に書く必要があります。
特に、購入理由については「どの業務に対して必要なのか」や「現状でどのような問題を抱えているため、損失を無くすために早急の購入が必要」、「物品の購入により、現在の作業時間を半分以下に短縮できる」など、会社のメリットにつながる点を明記しましょう。なお、記載事項は次の通りです。
- 件名:営業部ノートパソコン更新に関する申請
- 購入予定製品名:〇〇
- 価格:1台あたり:165,000円(税込)合計:3台で495,000円(税込)
- 購入予定日:2025年9月中旬
- 購入背景・理由:営業部で使用しているパソコンは導入から6年以上が経過し、起動やアプリ動作が著しく遅くなっています。営業ツールや資料作成ソフトの立ち上げに時間を要し、日常業務に遅れが発生しています。特に外出先でのプレゼンや提案書作成では対応がスムーズにできず、顧客対応にも悪影響を及ぼしかねない状況です。
- 期待される効果:起動や動作の高速化による作業効率アップ
- 申請者:営業部〇〇
「件名」や「購入予定製品名」の項目は、購入する物品との整合性に注意しましょう。「価格」の項目では、「一括支払いの金額なのか」または「月額課金の金額なのか」、「別途初期費用がかかるのか」など、事前に調査し、正しく記載する必要があります。また、消費税の記載についても内税か外税かの表記も見落とさないようにしましょう。
「購入予定日」と「購入理由」は、連動していなければなりません。「なぜ、その予定日に購入しなければならないのか」という部分が「購入理由」の欄で確認できることが大事です。
新規取引先との契約締結の稟議書は妥当性を明記しよう
新規取引先との契約締結では、稟議書の妥当性を明記する必要があります。記載事項は、次の項目を参考にしてください。
- 件名:新規取引先との契約締結に関する稟議申請
- 取引先名:株式会社〇〇
- 本社所在地:東京都港区〇〇
- 契約金額:月額 150,000円(税込)
- 契約期間:2025年9月~2026年10月(1年間)
- 契約締結日:2025年9月末日
- 取引理由:当社では営業活動の効率化と集客力向上を目的として、オンライン広告の強化を検討してきました。株式会社〇〇は広告配信の実績が豊富で、当社と同業界の企業でも成果を上げていることから、今回契約を締結することでマーケティング効果の最大化が期待できます。
- 期待される効果:デジタル広告配信の最適化による新規顧客獲得
- 契約リスクと対策:初期契約期間を1年間とし、成果検証後に更新可否を判断
- 申請者:営業部〇〇
稟議書の妥当性は、取引理由より判断されます。取引先企業の情報はそれらの理由を補足するための情報です。妥当性は、3つの指標から判断します。
- 稟議内容
- 手続きの進め方
- 提案内容がもたらす効果
これら3つの指標から妥当性(会社にとってのメリット)を伝えることが重要です。他社との契約で重要なポイントは、法的やビジネス上のリスクについての記載ではないでしょうか。「取引理由」にその点の理由が示されていなければ、決裁権者の承認は得られないでしょう。
システム導入の稟議書は導入目的や期待される効果を明記する
システム導入の稟議書は、導入目的と期待される効果を明記することが大事です。システムは、感覚的な理由で導入しても効果を期待できません。システム導入の稟議書では、現状の課題を定量的な数値データで記載し、導入前と導入後の期待される効果を明確に伝える必要があります。次の項目が記載する内容です。
- 件名:営業管理システム導入に関する稟議申請
- 導入予定システム:〇〇
- 導入費用:初期費用:0円 月額利用料:30,000円(税込) × 12か月 年間総額:360,000円(税込)
- 導入予定日:2025年9月
- 導入背景・理由:現在、案件管理はExcel、勤怠管理は別システム、経費精算は紙ベースと、管理が分散しており、 入力ミス・情報更新漏れ・承認フローの遅延が発生しています。 その結果、案件の進捗把握や原価計算がリアルタイムでできず、経営判断にタイムラグが生じています。〇〇を導入することで、案件管理・勤怠・経費精算をクラウド上で一元管理し、情報共有と承認スピードを向上させます。
- 期待される効果:案件別の工数・原価をリアルタイムで把握し、利益率改善に活用
- 費用対効果:承認フロー短縮により月10時間分の管理工数削減(年間約120時間)
原価計算の精度向上により赤字案件の早期発見 → 利益率2%改善見込 - 導入リスクと対策:操作習熟に時間がかかる可能性 → マニュアル配布とトライアル期間の設定
- 申請者:営業部〇〇
システム導入の稟議書で重要なポイントは、「導入背景・理由」、「期待される効果」、「費用対効果」などが客観的な数値データで明記されていることです。人材採用の場合は、どれほどの費用対効果を示すかは未知数の部分が多くなります。システム導入の場合は、現在の業務稼働状況(背景)を数値データで示すことで、導入後の「費用対効果」を具体的に提案できます。
稟議をスムーズに通すなら「ジョブマネ」のワークフローシステム

デジタルツールや業務アプリなどのシステム導入では、承認を得るための具体的な数値データで示した稟議書の作成が効果的です。稟議をスムーズに通すには、決裁権者に数値データで導入後のメリットへの理解を促しましょう。
既存業務の現況を数値データとして管理するには、ワークフローシステムが役立ちます。ワークフローシステムとは、稟議や決裁の流れをデジタル上で行い、申請・承認プロセスを可視化できるシステムです。企業はワークフローシステムの導入により次のメリットを期待できます。
- 申請・承認プロセスの進捗状況をリアルタイムで把握できる
- 稟議書の印刷や回付、保管が不要となる
- 稟議書作成時の人的ミス(印刷や記載漏れなど)を防止できる
- 稟議プロセスの記録による不正防止ができる
ワークフローシステムは、紙で稟議書を回付している企業の業務効率化につながります。そのワークフロー機能を備えた業務管理ツールがジョブマネです。
また以下にジョブマネの便利な機能をまとめました。
- スマホ対応で外出先でも承認ステータスを確認できる
- 19種類の項目から雛形を作成できるため業務を効率化できる
それぞれ順に解説します。
スマホ対応で外出先でも承認ステータスを確認できる
クラウド型の業務管理ツールのジョブマネは、会社のパソコンにインストールするタイプではありません。スマホ対応で外出先でも承認ステータスを確認できる点が効率的です。
承認ステータスなどの申請状況は、一覧表示により一目で把握できます。そのため、忙しい業務の合間でも承認ステータスの進捗状況の確認に時間を要しません。また、ジョブマネのワークフロー機能にはファイルの添付もできるため、電子化した稟議書に紙の資料を補足は不要です。
ジョブマネは、稟議書作成から承認までのプロセスをツール上で完結できます。しかもワークフロー機能を含めて17の機能をオールインワンで利用できます。
- ワークフロー機能
- スケジュール管理機能
- 工数管理機能
- 掲示板機能
- 顧客管理機能
- 原価管理機能
- 問合せ管理機能
- ToDo管理機能
- 経費精算機能
- 共有資料機能
- 見積管理機能
- 請求書発行機能
- レポート機能
- 電話メモ機能
- 商談履歴機能
- 案件管理機能
- 入金登録機能
ワークフロー機能を活用する場合は、ジョブマネのグループウエアプランの申し込みが必要です。グループウエアプランは、月額料金1,000円〜のコスト以外に初期費用のかからない点が特徴となります。
19種類の項目から雛形を作成できるため業務を効率化できる
ジョブマネのワークフロー機能は、19の項目から選んで目的に合った稟議書を作成できます。稟議書を作成する手間や時間を大幅に削減できる方法です。
ジョブマネによる稟議書の作成では、購買申請や勤怠申請など目的ごとに柔軟な承認経路を設定できます。
ジョブマネのワークフロー機能では、承認経路を申請種類別に承認者の設定ができます。設定できる承認者(決裁権者)は、申請書類ごとに5名までです。また、申請書類の設定は自由に追加できるため、状況に応じた申請書テンプレートを複数作成・保管できます。
いままで、稟議書の回付に費やしていた手間や時間は、ジョブマネのワークフロー機能により削減できます。削減できた時間を他の業務や売上拡大に向けた戦略策定の時間にあてることも可能です。