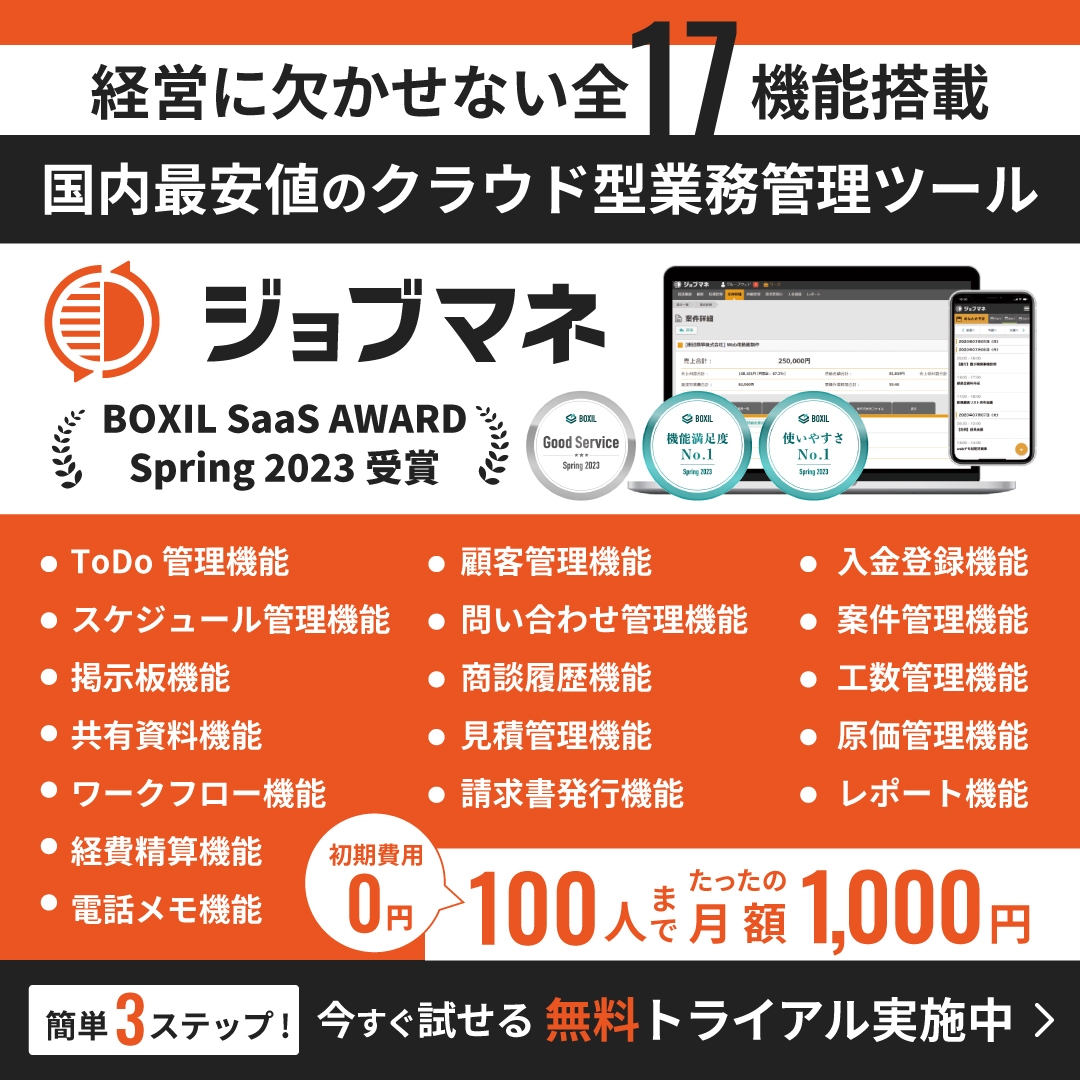外注管理とは?難しいと感じる理由から注意点まで徹底解説!
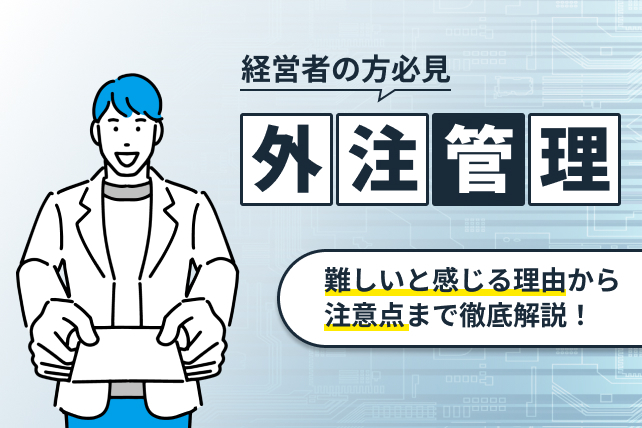
Web制作、システム開発、動画制作など、専門的な業務を外注するケースは少なくありません。
しかし、外注管理を適切に行わなければ、納期遅延や品質の不備、情報漏えいや支払いミスなど、さまざまなトラブルにつながってしまいます。
そこで本記事では、外注管理について基礎から解説するとともに、難しいと感じてしまう理由や、効率的に行う方法まで解説します。
「外注管理をミスなくスムーズに行いたい」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
記事の内容
外注管理とは委託先の業務状況を把握し適切に統制・管理する業務
外注管理とは、企業が外部企業や個人事業主などに業務を委託する際に、委託先における業務状況を把握し、品質やコスト、納期などを適切に統制・管理する業務です。
専門性を重視したい場合や、従業員にかかる人件費を抑えたい場合、コア業務に集中したい場合などに、業務を外注することは少なくありません。Web制作や動画制作、マーケティングなど、幅広い分野において外注管理の重要性は高まりつつあります。
外注管理とは、単純に外部に業務を委託するだけではありません。契約の締結から業務の進捗管理、品質管理、最終的な納期や支払いの管理まで幅広い業務が含まれており、適切に行うことによって企業としての競争力向上につながる業務です。
一方で、外注管理が不十分になってしまうと、納期が遅れてしまったり、品質が低下してしまうほか、コスト増加、情報漏えいなどのリスクが高まってしまいます。
また以下に外注管理を行う際に理解しておくべきことをまとめました。
- 外注管理に求められる役割と押さえておきたい基本的な流れ
- 外注管理が欠かせない業種や実務で直面する具体的な場面
- 外注管理が難しいとされる代表的な3つの大きな課題とは
それぞれ順に解説します。
外注管理に求められる役割と押さえておきたい基本的な流れ
外注管理に求められている重要な役割は、委託先との橋渡し役です。
社内で出された業務に関する要求をまとめ、正確に委託先に共有し、委託先の進捗状況を社内に適切に伝達する役割を担います。この役割を適切に果たすには、優れたコミュニケーション能力と、調整役としてのスキルも欠かせないでしょう。
外注管理の基本的な流れをステップ別に確認すると、以下の通りです。
1. 要件定義
はじめに、外注する業務内容・範囲・求める品質・納期・報酬条件について定義し、依頼の準備を進めます。
このタイミングで業務の棚卸しを行って、委託可能な業務の仕分けから行う場合も少なくありません。
2. 委託先選定と契約
これまでの実績や費用、資格・スキルなどをチェックし、業務の委託先を選定します。クラウドソーシングサイトや、紹介などを通じて選定するケースが多いでしょう。
契約を結ぶ際は、作業内容や範囲、納期、報酬、検収条件や品質基準などについて、漏れなく文書で明示します。
3. 発注
契約内容に基づいて発注書を作成・送付し、具体的な依頼内容を共有します。
このとき、進捗報告の頻度(週に一度・月に一度ミーティングを行うなど)や、コミュニケーションの方法(メール、ビジネスチャット、クラウドソーシングサイト上など)を取り決めましょう。
4. 進捗・品質管理
業務進行中は定期的に進捗を確認し、定例ミーティングなども行って納品の遅延を防ぎます。
レビューやフィードバックも徹底し、品質を維持することも欠かせません。
5. 納品受領と検収
納品受領後、依頼した内容と相違がなく、品質基準についても合格すれば、検収完了として検収書を発行します。
もしも不合格で差し戻しとなった場合は、修正・追加納品を依頼し、必ず検査に合格してから検収書を発行しましょう。
6. 請求・支払い
検収完了後、業務の受託者が請求書を発行し、発注者である企業は期日通りに支払いを実施します。
上記の一連の流れを進める際、外注管理担当者は、常に全体を俯瞰して管理することが求められます。あくまでも「自社の事業目標達成に外注をどう活用するか」という視点を持ち、単に委託先の管理にとどまらないことが重要です。
また、リスク管理も重要となるため、委託先の経営状況や技術に関して常に注意を払い、状況によっては代替案を準備しておくことで、スケジュールの遅延がないように備えることも求められます。
外注管理が欠かせない業種や実務で直面する具体的な場面
外注管理は、とくにIT・システム開発業界・広告業界・マーケティング業界・コンサルティング業界のほか、製造業や建設業において欠かせない状況となっています。なぜなら、これらの業界は業務の専門性が高く、すべての業務を自社のリソースで内製化するのは難しいためです。
例えばIT・システム開発業界では、プログラム開発やテスト・デバッグ作業、保守運用業務などを外注するケースが多く、システム開発のプロジェクトが大きい場合、一社だけでなく複数の業者に委託することもめずらしくありません。また、開発フェーズに沿って品質チェックポイントを確認し、スケジュールに遅れはないか、要件・仕様書に沿って開発されているかを把握するなど、非常に管理が複雑になります。そのため、外注管理の中でも高度な管理スキルが求められるでしょう。
一方で広告業界やマーケティング業界では、クリエイティブの制作やWebサイトの構築、SNS運用などを外注するのが一般的です。クライアントの求める成果を出すために、品質を確保しながらも遅延なくプロジェクトを進める必要があります。
コンサルティング業界では、リサーチやデータ分析、マーケティングなどを外注する傾向があり、BPOを活用するパターンもめずらしくありません。
製造業では、部品の製造や組立、物流業務などを外注するケースが多く、他の業界と同様に厳しい品質管理と納期管理が求められます。外注する際には、委託先の品質管理体制も定期的に監査することで、自社の品質基準を維持しなければなりません。また、原材料価格の変動や市場環境の変化も多いことから、契約条件の調整を行うことも多いでしょう。
一方、建設業界においては、各種工事や専門工事などを下請け業者に外注します。安全管理や品質管理はもちろん、工期が伸びないようにスケジュール管理を徹底するほか、現場での事故防止も外注管理の一環です。
このように、一口に外注管理と言っても、その業務は多岐にわたります。
外注管理が難しいとされる代表的な3つの大きな課題とは
外注管理が難しいとされる理由には、次に挙げる3つの大きな課題が隠されています。
- 外注先の進捗状況を正確に把握し管理するのが難しい
- 外注先との円滑なコミュニケーションが困難になる
- 担当部署や部門間の連携体制を整えることが不可欠
どのような理由で外注管理が難しくなっているのか、一つずつ確認していきましょう。
外注先の進捗状況を正確に把握し管理するのが難しい
外注先の進捗状況を正確に把握することは、外注管理における最大の課題と言っても過言ではありません。
多くの業務委託先は、複数の企業から外注されており、状況によっては自社の案件の優先度が低い場合もあります。また、どれだけのリソースを自社の業務に割いてくれるのかも、発注元からはなかなか掴めないでしょう。
その他にも、なかなか進捗報告がされなかったり、進捗報告の内容が不十分な場合には、後から問題が発覚し、予想外の大きな手戻りが発生するケースもめずらしくありません。
進捗報告では問題が隠ぺいされており、実際の稼働や成果と報告内容が異なるケースも考えられます。また、外注先の能力・技術が想定していた基準に届かず、プロジェクトが思うように進まない恐れもあるでしょう。
このような状況を避けるためには、定期ミーティングの頻度を上げたり、中間成果物のレビューを実施したりと、進捗報告の方法を変える必要があります。
外注先との円滑なコミュニケーションが困難になる
外注管理では、外注先と円滑にコミュニケーションを取れるかどうかも大きな課題となります。
外注先とは物理的距離があるため、何か急ぎで連絡を取りたい場合にも、迅速にコミュニケーションが取れないことも少なくありません。とくに、日本国内ではなく海外の業者やクリエイターに業務を委託する場合、時差や言葉の壁によって、コミュニケーションがさらに遅延することも多いでしょう。
仮にコミュニケーション不足が発生した場合、次のようなリスクにつながります。
- 誤解や要件不一致が起こり、成果物が期待水準を満たさず品質が低下する
- フィードバックの遅延や手戻りが増え、納期が遅延してしまう
- 手戻り・非効率により追加工数や再作業費が生じる
- 進捗や品質が可視化されず、プロジェクト管理が難しくなる
- 情報共有漏れにより意思決定が遅れ、問題の早期発見や是正ができない
- 契約解消や評判低下などレピュテーションリスクに波及する
このような状況を避けるためには、外注内容について文書化を徹底するほか、定期的なミーティングの実施が欠かせません。また、メールやチャット、クラウドソーシングサイトなど、複数チャネルでコミュニケーションを確保することも効果的でしょう。
担当部署や部門間の連携体制を整えることが不可欠
外注管理においては、担当部署や部門間の連携体制を整えることも欠かせません。
事業を展開する際、営業・マーケティング・経理・品質管理・技術など、幅広い部署が関係するケースが多いです。そのため、各部門との情報共有や役割分担について整理し、円滑に連携する必要があります。
仮に部署・部門間の連携が不足してしまうと、外注先への指示で矛盾が生じてしまったり、品質基準がバラバラになったり、支払い処理に遅延が生じたりと、さまざま問題につながりかねません。例えば、営業部門が外注に共有した業務内容と、技術部門が認識している業務内容に違いがあった場合、外注先は混乱し、プロジェクトは停滞してしまうでしょう。
また、複数の部署・部門がプロジェクトに関与しているにもかかわらず、外注管理の責任者が曖昧なままだと、意思決定がスムーズに進まないため注意が必要です。外注管理における承認ワークフローについて、事前に流れを確認しておくことをおすすめします。
加えて、外注する際の情報が特定の部門・部署や担当者に固まらないように、情報共有の方法についても仕組みを構築しておきましょう。
外注管理が楽になる!マニュアル化すべき基本の4ステップ
外注管理を効率化し、品質を向上させるためには、業務のマニュアル化が不可欠です。標準化されたプロセスに従って外注管理を行うことで、担当する人のスキルや経験に依存することなく、安定した外注管理を実現できます。
具体的には、次の4つのステップについてマニュアル化しましょう。
- 選定した外注先と条件を擦り合わせた上で契約を締結する
- 必要事項を記載した発注書を作成し外注先に対して送付する
- 外注先の進捗状況を確認しながら適切な方法で管理・対応を行う
- 外注先からの納品物を確認し請求書を受領して支払いを完了する
それぞれ順に解説します。
選定した外注先と条件を擦り合わせた上で契約を締結する
外注管理においてはじめに重要になるのが、適切な委託先の選定と契約の締結です。最適な委託先を選定した上で、詳細な契約条件について擦り合わせる必要があります。
契約条件の擦り合わせでは、次のポイントについて詳細に交渉し、文書として明示しましょう。
- 業務範囲
- 品質基準
- 納期
- 価格
- 支払い条件
- 知的財産権
- 機密保持
- 損害賠償 など
なかでも注意が必要なのが、知的財産権についてです。納品された成果物の権利の帰属先、既存技術の使用許可、第三者の権利侵害に対する責任分担などについて明確に記載し、権利に関するトラブルを未然に防ぎましょう。
また、機密保持についても慎重に擦り合わせが必要です。情報漏えいによる信用失墜、取引先とのトラブル、損害の発生などを防ぐために、取り扱う情報の範囲やその保管方法・廃棄方法、第三者への開示制限などを詳細に定めてください。
必要事項を記載した発注書を作成し外注先に対して送付する
契約を締結したら、必要事項を記載した発注書を作成し外注先に対して送付する必要があります。
発注書には、以下の内容を中心に漏れなく記載しましょう。
- 業務内容
- 仕様
- 納期
- 価格
- 支払い条件
- 品質基準
- 連絡体制 など
業務内容は、作業内容や範囲についてわかりやすく定義し、成果の仕様や形式も含めて詳細に記載してください。例えば、システム開発について外注する場合、開発するシステムの機能や技術仕様、動作環境、テスト内容などについて細かく明記しましょう。
仕様書や要件定義書がある場合は発注書に添付し、業務内容について正確に理解できるように配慮することも重要です。また、仕様変更が発生した場合の対応についても記しておくと安心でしょう。
納期については、最終納期だけでなく、中間納期や段階的な納品スケジュールも明記しておくことで、進捗管理を効率化できます。また、問題の早期発見と解決もしやすくなる点がメリットです。
品質基準を記載する際には、検収基準や品質確認方法について述べ、どのような条件を満たせば検収合格となるのか、不合格となった場合の流れや修正方法などについて記しましょう。
連絡体制に関しては、主な連絡方法や定期ミーティングの頻度、緊急時の連絡先などを明確にし、進捗報告のタイミングについても擦り合わせておくことで、コミュニケーション不足を防いでください。
発注書の作成・送付後は、委託先からの受領確認と内容確認を欠かさず行い、疑問点・不明点がないかチェックしましょう。業務を進める前に疑問を解消することで、その後のトラブルを防止できます。
外注先の進捗状況を確認しながら適切な方法で管理・対応を行う
外注先に発注してからは、進捗状況を確認しながら適切な方法で管理しましょう。定期的な進捗確認は、課題の早期発見と解決につながります。
進捗確認を行う方法は、以下の通りです。
- 定期報告
- 定例会議
- 現地確認
- 中間成果物レビュー
委託する業務内容に合わせて、上記のような方法を組み合わせて行いましょう。
定期報告では、作業の進捗率や完了した作業、発生した課題やリスクなどを共有してもらい、定例会議では、より詳細な進捗状況、課題共有、解決策の検討などを実施します。言った・言わないのトラブルを防ぐためにも、会議の議事録は必ず作成し、決定事項と担当者を明確にしておきましょう。
中間成果物のレビューを行う場合には、品質確認だけでなく最終成果物の品質予測も重要な作業です。成果物の品質に問題が生じると予測された際には、早期に修正を指示し、品質向上を図ります。
外注先からの納品物を確認し請求書を受領して支払いを完了する
外注先から納品されたら、成果物を確認して検収し、請求書を受領して支払いを完了しましょう。このフェーズにおける処理が不適切になってしまうと、業務委託先との信頼関係に影響します。今後の取引に支障をきたすリスクが高いため、慎重にかつ丁寧な対応が重要です。
検収作業では、品質基準に基づいて納品物を確認します。検収期間がどの程度かかるのかは事前に周知し、検収期間中に問題が発見された場合の対応、追加作業、合格条件などについても明示しておきましょう。追加費用の取り扱いについても擦り合わせておくことで、金銭に関するトラブルを防ぎます。
請求書の確認では、契約金額との整合性や支払い条件などについてチェックし、請求内容にミスや疑問が見られる場合は、外注先に速やかに確認して対応を求めましょう。
支払い処理については、遅延や入金ミスなどが発生しないように細心の注意が必要です。支払い遅延・ミスは委託先の資金繰りに影響するほか、信頼関係の喪失にもつながるため、正確な処理を心がけてください。
外注管理の注意点4選!トラブル防止の方法を解説
外注管理では、さまざまなリスクが存在します。そのため、トラブルを未然に防ぐための対策が欠かせません。ここからは、次に挙げる4つの観点から、具体的な注意点と対策方法を解説します。
- 情報が外部に漏えい・流出しないようにしっかりと管理する
- 納期の遅れや品質の不備などの外注トラブルにあらかじめ備える
- 具体的なスケジュールを設定し業務の進捗状況を把握する
- 外注先との行き違いを防ぐため定期的に連絡や情報交換を行う
それぞれ順に解説します。
情報が外部に漏えい・流出しないようにしっかりと管理する
業務を外注する場合、情報が外部に漏えい・流出しないように慎重に管理しなければなりません。
仮に機密情報や個人情報などの重要な情報が外部に流出した場合、次のようなマイナスの影響があります。
- 信用失墜とブランド価値の低下
- 顧客離れや営業機会の損失
- 顧客・取引先・従業員への損害賠償請求の発生
- インシデント原因の究明や再発防止のための業務停止
- 営業秘密や研究開発情報の流出により競争優位性の喪失
- 追加のセキュリティ対策費や問い合わせ対応のコールセンター設置など、追加費用の発生
上記のような事態にならないように、情報漏えいを防ぐためには、委託先のセキュリティ体制を事前に把握しなければなりません。委託先の企業の内部統制が整備されているか、従業員へのセキュリティ教育は徹底されているか、セキュリティ認証は取得しているかなどをチェックし、リスクが低いと判断できる業者に外注しましょう。
また、秘密保持契約(NDA)の締結も業務内容によっては必要です。情報の取り扱いや保管期間、廃棄方法、違反が判明した際の損害賠償についてまで定めることで、情報漏えいにつながるリスクを最小限に抑えられます。
提供する情報は必要最低限に抑え、外部からのアクセス制御、システムのログ管理まで徹底するなど、社内で行えるセキュリティ対策も欠かさず行いましょう。
納期の遅れや品質の不備などの外注トラブルにあらかじめ備える
外注した業務の納期が遅れてしまう、品質が伴わないといったトラブルについても、あらかじめ備えておく必要があります。
納期の遅延や品質不備に備えるには、委託先の選定を慎重に行うことが必須です。これまでの対応実績から能力・技術力を判断し、信頼して依頼できるかを十分に考慮して選定しましょう。また、そもそもの納期設定に無理がある場合や、報酬に対して品質要求が高すぎる場合はトラブルに発展しやすいため、依頼内容は現実的にすることも欠かせません。
また、納期の遅延があった場合、どのように対応するか前もって決めておくことも重要です。数日ほどの軽微な遅延は許容する一方で、数週間以上などの大幅な遅延については損害賠償を請求するなど、ペナルティについて擦り合わせておきましょう。
品質の不備に関しては、納品時のチェックだけでなく段階的なチェックフローを設けることで、検収時の手戻りを防止できます。中間レビューで品質を把握し、問題がある場合も早期に発見できるように対策してください。
具体的なスケジュールを設定し業務の進捗状況を把握する
業務を外注する場合、曖昧なスケジュール設定だとトラブルにつながります。できるだけ具体的にスケジュールを設定し、業務の進捗状況をリアルタイムに把握しておくことで、問題を早期に発見できる体制を整えましょう。
スケジュールを設定する際には、作業項目ごとの期限を最終的な納期から逆算して設定します。作業項目を曖昧に設定してしまうと、スケジュールの遅延につながりかねないため、進捗を把握しやすいようにできる限り細分化しましょう。
また、進捗報告の仕組み化も欠かせません。進捗報告に関するルールを設定し、状況を定期的に把握できる環境を整備します。進捗報告の頻度は業務内容によって異なりますが、月次・週次・隔週で行うパターンが多いでしょう。
仮に進捗が遅延した場合も迅速に対応できるように、対応策(リソースの追加、スケジュール調整など)についても事前に考慮しておくと安心です。
外注先との行き違いを防ぐため定期的に連絡や情報交換を行う
外注先とのコミュニケーション不足は、外注管理におけるさまざまなトラブルの要因となります。認識のすれ違いや誤解、重要な情報の伝達漏れなどを防ぐためには、定期的に連絡を取れるように、コミュニケーション体制を必ず整備しましょう。
コミュニケーション体制を整備するには、連絡方法・ツールや、連絡頻度、内容、担当者などをはじめに設定します。日常的な連絡に関してだけでなく、ミーティングの頻度や使用するツール、緊急時の連絡方法についても考慮し、コミュニケーションを円滑に行える環境を整えてください。
また、重要な情報に関しては、口頭によるコミュニケーションだけでなく、仕様書やメールなどの文書に残すように注意が必要です。言った・言わないのトラブルを未然に防ぐために、後から情報を参照できる媒体で伝達するよう心がけましょう。
外注管理はエクセルでできる!デメリットは入力ミスやデータ共有
経費や売上データ、顧客リストの管理など、さまざまなビジネスシーンで活用されているエクセルですが、外注管理においても便利なツールです。
エクセルは、初期導入費用を抑えられるだけでなく、汎用性に優れているため、外注管理での活用も問題ありません。エクセルを外注管理に活用すれば、「外注管理ツールのコストを抑えたい」という中小企業のお悩みにも応えられます。また、多くの人が操作に慣れていることで、ツールを導入する際の教育コストも抑えられるのは大きなメリットでしょう。
しかし、エクセルによる外注管理には限度があるのも事実です。具体的には次のようなデメリットがあります。
- 自動化できる範囲が限られていることで入力ミスが発生しやすい
- データの整合性が十分に確保できない
- 複数人でデータを共有する際にバージョン管理が難しい
- セキュリティの脆弱性がある
エクセルで外注管理を行う場合には、上記のデメリットに注意しなければなりません。
エクセルで外注管理表を作成するときに必要な項目一覧
エクセルで外注管理表を作成する際には、管理すべき項目を体系的に整理することで、情報を漏れなく記録できる表にする必要があります。
外注管理に必要な基本的な項目は、次の通りです。
外注先名称
外注先名称は、外注管理の基本情報です。正式な法人名、あるいは事業者名を記入します。類似した名称の企業・業者との混同を避けたい場合は、企業コードや識別番号も記載すると安心です。
担当部署
担当部署には、業務の外注についてどの部署が管理するかを記載します。営業部、マーケティング部、製造部、情報システム部・技術部など、業務を外注している部署について記入してください。
担当者名
担当者名には、社内の担当者と外注先の担当者の両方を記載しましょう。電話番号やメールアドレスなどの連絡先も記載しておくと、円滑なコミュニケーションが叶います。担当者の変更があった場合は、更新日を記録した上で最新の情報に更新してください。
支払条件
支払条件は、外注費の支払いに関するルールを詳細に記す欄です。消費税の取り扱いや源泉徴収の有無なども記載しておきましょう。
支払方法と支払期日
銀行振込、手形、現金などの支払方法や、請求書受領から支払いまでの日数、月末締め翌月末払いなどの支払タイミングを詳細に記録します。銀行振込の場合は、振込先の銀行名や支店名、口座番号や名義まで管理する必要があります。
金額
契約金額など、外注における金額に関する情報を記載します。単価契約を結んでいる場合は基本単価、数量契約の場合は数量と単価のどちらも記載し、報酬のミスがないように対策しましょう。消費税込み・税抜きの区分も明記することで、税率変更時の対応もスムーズです。
業務内容
業務内容欄には、外注する業務の具体的な内容を記載します。作業内容・範囲・成果物の仕様、品質基準などを明記し、依頼時や検収時の対応をスムーズにしましょう。業務内容によっては、別途仕様書を作成し、その参照先を記載してください。業務内容の変更があった場合には、変更履歴や変更範囲についても忘れずに記載します。
納期
最終的な納期・中間納期のほか、納期変更があった場合の履歴、遅延理由なども記します。
専用システムの導入で外注管理をスムーズに進められる
エクセルによる外注管理の課題を克服するには、専用システムの導入も検討しましょう。
先にご説明したように、外注管理はエクセルでも問題ありません。しかし、より効率的に管理したい場合や、ミスなくリアルタイムに情報を管理したい場合、エクセルでの管理には限界が生じます。
一方、専用システムを導入する最大のメリットは、外注管理業務に特化した機能を利用できることです。専用システムには、契約管理や発注管理、進捗管理や支払管理など、外注管理に必要な機能が搭載されています。そのため、エクセルよりも管理業務を効率化でき、業務品質の向上も同時に叶うのが利点です。
外注管理をミスなくスムーズに進めたい場合は、エクセルではなく専用システムの導入を検討してみましょう。
外注管理は「ジョブマネ」の案件管理機能で一目で把握!

ミスなく外注管理を行うためには、専用システムの活用が不可欠です。「どのツールを導入したらいいのか?」とお悩みの方には、多くの企業で採用されている「ジョブマネ」をおすすめします。
「ジョブマネ」では、案件管理機能を利用でき、案件名・売上区分・顧客名・売上金額・担当者・進捗状況などを一覧で把握可能です。管理基準に合わせて表の項目はカスタマイズできるため、自社仕様の外注管理表を簡単に作成できます。
クラウド型のシステムなので、情報をリアルタイムに管理でき、エクセルのようにバージョン管理に戸惑うリスクもありません。
外注先情報を簡単に登録・検索できるのでミスを防げる
外注管理において重要なのは、外注先情報を正確に管理することです。外注先名称や担当部署、担当者名、業務内容や支払額などを適切に管理しなければ、情報の伝達ミスや納期遅延、支払いミスなどのさまざまなトラブルにつながりかねません。
その点「ジョブマネ」では、外注先情報を簡単に登録・検索できるため、外注先情報に関するミスを未然に防止できます。エクセルを利用している場合、入力ミスが発生しやすいだけでなく、情報の検索性も低いのが懸念点ですが、「ジョブマネ」であればそのようなデメリットもありません。
必要な情報を入力するだけで見積書や発注書をすぐに作成できる
「ジョブマネ」は、外注先情報の管理だけでなく、見積書や発注書を簡単に作成できるのも人気なポイントです。
直感的に操作できる画面のため、これまでにエクセルしか使ったことがない場合も気軽に操作でき、見積書・発注書の作成にかかる負担を軽減できます。テンプレート機能も用意されているため、一から作成する手間をカットできるのも大きなメリットです。
企業ロゴや電子角印の記載、ワンクリックによるPDF出力などの便利な機能が満載のため、外注管理業務や、付随する見積書・発注書の作成業務までまとめて効率化できます。