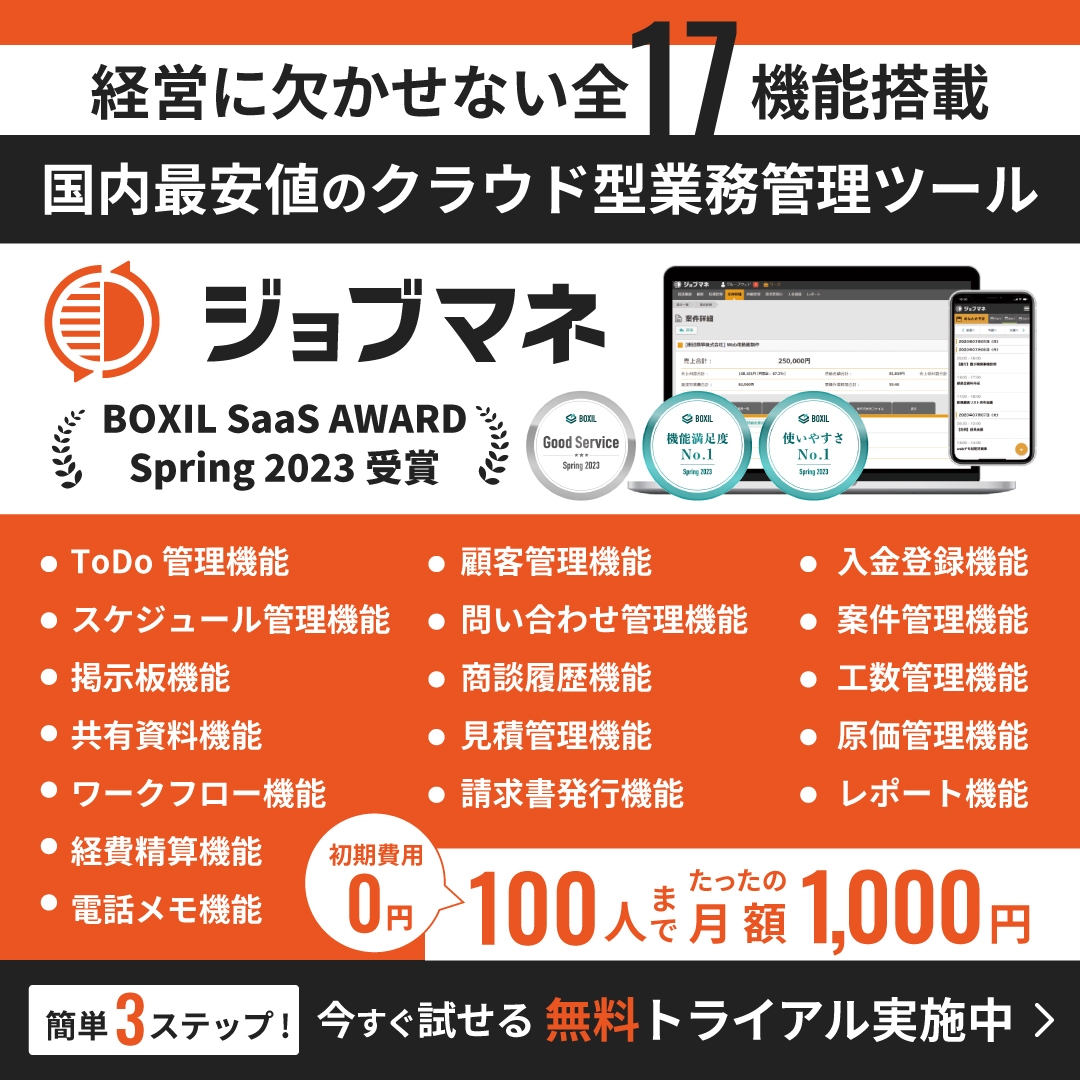原価管理とは?目的と管理方法をわかりやすく解説!
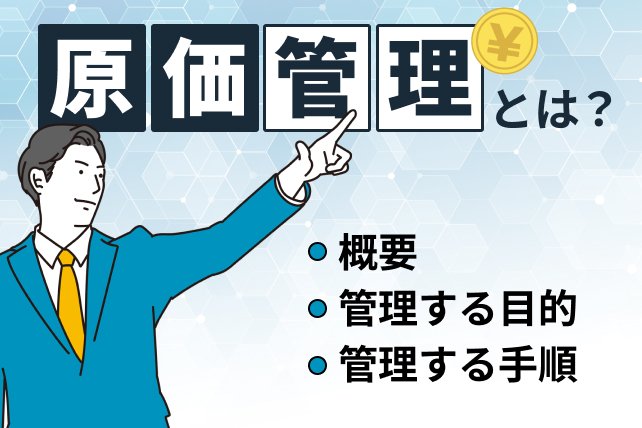
企業の原価管理は、収益性を維持するための重要なプロセスです。適切な原価管理は経営判断の精度を高め、戦略的な意思決定を支える基盤となります。製品やサービスの提供に関わるコストを適切に把握し、分析・管理することで、支出の適切な削減や生産性の向上、価格競争力の強化につながります。
また、原価管理にはデータの可視化が前提であり、生産にかかるデータの持続的な集積と分析、正確性が必要です。
企業税務の観点からも、記録・分析にまつわるエラーを防ぐ仕組み作りや人的エラーの排除も重要だといえます。
このページでは原価管理の基本や順序、原価管理における課題や解決策について解説します。
記事の内容
原価管理とはプロジェクト完了までの原価を管理すること

原価管理とは、企業が製品やサービスの製造・提供にかかるコストを適切に把握し、管理する手法を指します。
原価管理によって継続的な改善を実施するプロセスは、企業利益の最大化や適切なコスト削減のために非常に重要です。
原価管理は企業利益の最大化やコストの可視化、リスク管理、経営判断の根拠となるデータ獲得を目的としています。
- 利益率の向上
- コストの可視化
- 損益分岐点の把握
- リスク管理
- 経営判断の支援
原価管理はさまざまな業種で重要視されている重要なプロセスです。適切な原価管理を行うことで、企業は競争力を高め、持続可能な成長を実現できます。
原価管理では、各製品やサービスにかかる費用を詳細に可視化し、損益分岐点の把握や適切な価格設定につなげます。
また、原価の変動要因の把握や、起こり得るリスクへの早期対応を目指します。これらの原価データをもとにした分析は経営計画や予算編成に非常に重要です。
原価管理の流れは以下の4つのプロセスに沿って実施します。
- 標準原価の設定
- 実際原価の計算
- 差異分析
- 改善活動
目標となる原価を見積もり(標準原価の設定)、製造後には実際にかかった原価を算出します。在庫がある場合は棚卸しデータが必要です。目標として設定していた標準原価と実際にかかった原価の差異を分析し、利益見積もりの修正やコスト改善、効率改善のための具体的な施策につなげます。
原価を正確に把握するには、長期的なデータの集積や管理が必要です。原価管理4つのプロセスについては後半でも解説していますのでご確認ください。
原価は大別して製造原価と売上原価に分けられる
原価管理に必要な原価データは、大きく分けて「製造原価」と「売上原価」の2種類に分類されます。
製造原価は製品を製造する際にかかる費用の総額であり、主に以下の3つの費用から構成されます。
- 材料費:製品を作るために必要な原材料や部品の購入にかかる費用
- 労務費:製品の製造に直接関与する作業者の賃金や手当
- 経費:製造に関連する間接的な費用
以下の図で詳しく解説します。

製造原価は製品の製造プロセスにおいて直接的または間接的に発生するものであり、主に材料費、労務費、製造に関連する光熱費や減価償却費などが含まれます。
製造原価は製品が完成した時点で計上され、企業が製品を市場に供給するためのコスト構造を明らかにし、適正な販売価格を設定するために使用されます。
一方、売上原価は製品やサービスの提供に関わるすべてのコストで、販売された製品にかかった費用を指します。
また以下に売上原価の例をまとめました。
- 商品の仕入れ代金
- 原材料費
- 製造ラインの人件費
- 外注費
- 商品の運搬費や保管費などの付随費用
売上原価は製品が販売されて売上となった時点で計上され、販売された商品の仕入れや製造にかかった費用など、販売された商品のみに関連する費用が含まれます。売上原価は以下の計算式で求められます。

売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高−期末商品棚卸高
売上原価には販売費や一般管理費、運搬費など、販売に関連する費用が含まれますが、実際に売上に貢献した製品コストのみを計上します。損益計算書において売上高の直下に記載され、売上高から売上原価を引くことで売上総利益(粗利益)が算出されます。
このように、同じ原価でも「製造原価」と「売上原価」には大きな違いがあり、業種によって売上原価に含まれる費用の範囲が異なります。売上原価の場合は実際に販売された製品にかかる費用が含まれ、製造原価の場合は製品を製造するためにかかったすべての費用が対象です。製造原価には、売れ残った在庫にかかる費用も含まれますが、売上原価は販売された製品に関連する費用のみを計上します。
売上原価に含まれる費用は製造業やサービス業など業種で異なる
売上原価については、製造業やサービス業、小売業など、業種によって含まれる費用に特徴があります。
製造業では原材料費や製造労務費が主な要素となり、サービス業では人件費やシステム運用費が大きな割合を占めます。売上原価の計算やその内容は業種によって異なるため、自社の業種に特有の要素についての理解が重要です。
まずは製造業の売上原価に含まれる費用について見てみましょう。
- 材料費
- 直接労務費
- 製造間接費
- 外注費、輸送費
製造業の売上原価は製品を製造するために必要な原材料費や製品製造に関わる従業員の人件費が中心です。
また、設備の水道光熱費や減価償却費、外注費、輸送費が含まれ、直接的に製造に関わるコストを計上します。
サービス業における売上原価では、外部委託に関わる外注費や、特定のプロジェクトに直接関与するスタッフの人件費が中心です。提供したサービスに直接かかった費用を計上します。
- 外注費
- 直接的な人件費
サービス業では、物品の仕入れや原材料費は基本的に発生しないため、外注費や直接的な人件費がコストの中心です。サービス業における外注費としては、ソフトウェアの開発費やマーケティング・広告費、グラフィックデザインやウェブデザイン、事務作業の外部委託費などがあります。
このように売上原価の構成要素は業種によって異なり、各業種の特性に応じた費用の取り扱いが求められます。製造業や建設業では製造・建設に直接関わる材料費・人件費が中心であり、小売業や卸売業では、商品の仕入れ費用が売上原価の中心を占めます。
また、業種による特徴に加えて企業により経営方針にも違いがあります。そのため、原価管理には標準的なルールをもとに企業の独自ルールを設定し、長期間にわたるデータ収集、原価計算、データの管理が必要です。
仮に、棚卸資産の計上漏れや原価計算に誤りが生じると、原価が過大に計上されていた場合に税務面での問題が発生します。そのため、原価管理はデータの集積・分析だけでなく、エラーの検出も重要です。数値傾向の把握や異常値の抽出、不一致項目がある場合のアラートなど、専用システムの力を借りることで多くの課題を解決できます。
原価は材料費・労務費・経費の3形態に分類される

企業経営で中心的な役割を果たす原価は製品・サービスの提供完了までにかかる費用を指し、「材料費」「労務費」「経費」の3要素で構成されます。
1.材料費
材料費は、製品の製造に直接使用される原材料や部品の費用です。
- 主要材料費:製品の主要な構成要素となる材料の費用
- 買入部品費:製品に組み込まれる部品の費用
- 補助材料費:製造関連の補助材料の費用
主要材料の費用や、製品に組み込まれる部品費のほか、製造に直接関わる燃料費や製造過程で補助的に消費される消耗品費が含まれます。材料費は製造量が増えるほど増大する費用です。
2.労務費
労務費は、製造に従事する従業員や臨時工員の給与や手当を指します。
- 直接労務費:製品の製造に関わる従業員の人件費
- 間接労務費:製品の製造を間接的にサポートする従業員の人件費
直接労務費は製品の製造に直接関わる従業員に支払われる賃金です。間接労務費は、工場管理者や工場事務員、運搬者など、製造を間接的にサポートする従業員の人件費が含まれます。労務費は労働時間が長くなるほど増加します。
また、残業や休日出勤が発生すると割増賃金が発生するため、繁忙期には労務費が増える傾向にあります。労働基準行政の法制度を遵守しつつ、適切な人員配置やシフト管理、業務の効率化が重要です。
3.経費
経費には、工場の水道光熱費や設備の減価償却費などの製造間接費、外注費、広告費や販売促進費などが該当します。
- 製造間接費:工場の光熱費、設備の減価償却費など、製造活動に関連する費用
- 販売費および一般管理費:販売促進費、広告費など
材料費と労務費以外のすべての費用を指し、工場や作業場の維持費、地代家賃、修繕料があります。経費は製品の製造やサービス提供に直接関与しませんが、事業運営に必要なコストとして算入します。
これら原価の3要素の正確な把握が原価管理の基本であり、製品別・部門別・プロジェクト別に分類して算出します。詳細な数値の把握、集計、管理は企業の利益率向上やコスト削減に不可欠です。原価を正確に把握することで、適切な価格設定や利益管理が可能になり、効率的な経営につながります。
原価管理の目的は原価を把握することによる利益向上
原価管理の最大の目的は、原価を適切に把握し、的確なコントロールによって利益を最大限に向上させる点にあります。企業が製品やサービスを提供する際に発生するコストを正確に把握し、利益を最大化するための戦略的な取り組みです。
企業は原価管理を通じて製品の製造にかかるコストを正確に把握することで不要なコストの削減や収益性の向上につなげます。
また以下に原価管理の目的をまとめました。
- 利益率の向上
- リスク管理
- コストの見直し
- 戦略的意思決定の支援
- 財務の健全性の確保
原価管理で最も重要な目的は利益の最大化です。企業は製品やサービスの原価を正確に把握することで適切な販売価格を設定し、利益を確保できます。原価を管理することで適切なコスト配分を実現でき、利益率の向上につながります。
適切なコストの見直しには、材料費や労務費、経費といった「原価の三要素」の分析が不可欠です。製造やサービス提供にかかるコストの見直しにより、効率的な資源配分を実行できます。
原価の把握は原価変動などの影響を抑えるリスク管理につながる
原価の把握は、原価変動によるリスクを管理するためにも重要です。
市場には必ず外部要因・リスクが関わってきます。市場の変動や原材料の価格変動、為替レートの変動など、外部要因が原価に影響を与えるため、原価管理は重要な経営判断に関わります。
また以下に外部要因・リスクについてまとめました。
- インフレ進行と原材料費の高騰
- 市場競争の激化
- 需要の変動
- グローバル化による国際競争
市場環境や経済状況の変化は、原価管理に多大な影響を与えます。現状の正確な把握だけでなく、適切な外部情報・データの収集も原価管理には必須であり、あらゆるデータが経営方針の決定に大きな影響を及ぼします。
適切な原価管理は経営判断の精度や企業運営にも影響を与え、企業の持続的な成長を支える重要な要素となるのです。
仮に、原価管理が不正確であった場合、企業にとって重大なリスクをもたらします。原価計算が不正確であると実際のコストが想定を超え、プロジェクトの予算超過を引き起こす可能性があるため注意が必要です。以下に不正確な原価管理によるリスクの可能性をまとめました。
- 利益の過小評価または過大評価
- 赤字案件の発生リスクの増加
- 価格競争力の低下
- 財務管理への影響
原価管理の不正確さは、利益の誤評価、赤字案件の発生、経営判断の誤りなど、さまざまな問題につながる可能性があります。正確な経営判断には、正確な原価管理が不可欠です。原価管理の精度を高めるためにも、適切な管理システムの導入も解決策として推奨されます。
原価計算は原価管理に内包される作業なので違う意味を持つ
原価管理と似た名称として「原価計算」や「予算管理」があります。それぞれの用語の違いを確認しておきましょう。
まず、原価計算は製品の製造前後における計算作業を指し、コストの算出に焦点を当てています。一方、原価管理は原価計算による算出結果を分析して、改善策を実施する一連の活動を指します。
- 原価計算=製品の原価を計算
- 原価計算による結果+差異分析+改善活動→原価管理
原価計算は原価管理の一部です。正確な原価計算が行われることで、適切な原価管理へとつながります。原価計算で得られたデータをもとに、原価管理では差異分析や改善活動・コストの最適化などの事業修正が実施され、企業内で継続的なPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を実現できます。
予算管理と原価管理の違いは管理する対象の広狭
予算管理と原価管理の主な違いは、管理する対象の広さにあります。予算管理は企業全体の収支を対象とし、売上や費用全般を含む広範な業務であり、原価管理は個々のプロジェクトの原価を管理する行程です。
- 予算管理=企業全体の収支(売上や費用全般を含む)
- 原価管理=各プロジェクトの予実管理
予算管理では、まず予算案を作成し、承認された予算にもとづいて実績値との比較を行います。
原価管理では、主に製品やサービスの提供に直接関わるコストに焦点を当てて管理します。実際のコストと目標値である標準原価の差異を分析し、コストの分析や収益改善に向けた取り組みを継続的に実施します。
原価管理の仕事内容は4つの手順で進める
原価管理は、標準原価の設定、実際原価の計算、差異分析、改善活動の実施という4つの手順で進行します。
- 標準原価の設定
- 実際原価の計算
- 差異分析
- 改善活動
4つのプロセスを順に実行することで、企業はコストを正確に把握できるようになり、利益最大化のための戦略立案が実現できます。
原価管理のPDCA(計画、実行、評価、改善)である各プロセスについて確認しましょう。
標準原価を設定することで製造前予算を立てやすくする
最初のステップである標準原価は、過去の実績や市場調査にもとづいて設定される原価です。
製品やサービスの製造に必要なコストの見積もりを実施し、材料費、人件費、間接費などを含めて算出します。製品やサービスの各コスト実績が反映された原価で、正常な生産条件下で期待される原価を設定します。
- 製品1単位あたりの標準的な材料費、労務費、間接費を予測の上で設定する
- 過去の実績データや市場調査をもとにした、現実的かつ達成可能な数値を基準にする
- 製品やサービスの製造にかかる理想的なコストを示す基準を目標として設定する
標準原価は過去データや標準的なデータをもとに設定され、プロジェクトで期待される目標値です。標準原価は原価管理の基礎となるため非常に重要なステップであり、標準原価の設定によって、製造や企画ごとの予算立案が明確になります。
原価計算を行うことで製造後の実際原価を算出する
次に、実際に発生した製造コストをベースとして実際原価を算出します。
製造業では、個別原価計算(特定の製品ごとに原価を計算)と総合原価計算(大量生産品の平均原価を計算)を使い分けることがあります。これに対し、サービス業では、プロジェクト単位での原価計算が一般的です。
製造業を例に、実際原価の算出式を見てみましょう。直接材料費、直接労務費、製造間接費などの各種コストをもとに集計します。
実際原価=直接材料費(A)+直接労務費(B)+製造間接費(C)
※(A)直接材料費=実際価格×実際消費量
※(B)直接労務費=実際賃率×実際作業時間
※(C)製造間接費の集計
実際原価の算出により、詳細な原価計算が可能となり、後の分析や改善活動の基礎データとして活用できます。
標準原価と実際原価の差異分析を行うことで原価を見直す
差異分析では、標準原価と実際原価の差異を分析します。差異の発生源(材料費、労務費など)や差異の種類(価格差異、数量差異など)、生産効率の変化、内部要因なのか外部要因なのかを分析します。
また以下に差異分析の例をまとめました。
- 直接材料費における差異:材料の購入価格が予想よりも高かったケース
- 直接労務費における差異:従業員の人件費が想定よりも高かったケース
- 製造間接費における差異:工場の運営コストが予想よりも高かったケース
差異の原因を特定できると、有利差異か不利差異かの判断も可能です。この分析により原価管理の効果を測定し、改善の余地がある領域が判明します。
また、差異が拡大傾向にある場合はコスト管理の見直しが必要です。市場価格の変動や市場価格・原材料価格等の外部要因の場合は情報収集を進めましょう。
差異分析の結果に基づいて問題点があれば改善する
差異分析の結果に基づいて、問題点があれば以下のような改善策を立案し、実施します。
- 仕入れ先・仕入れ価格の見直し
- 価格設定の見直し
- 労働時間の短縮を含めた生産プロセスの効率化
- 間接費の見直し、管理強化
生産プロセスの効率化、原材料費の見直し、調達方法の改善、労働生産性の向上など、対策できる分野は多岐に渡ります。
たとえば、原材料費が標準原価を上回っている場合、購入価格の上昇なのか、使用量の増加なのか、原因を特定します。原材料費の増加が課題の場合、安価な代替材料も視野に入ってきます。次回のプロジェクトで標準原価に近づけていくことが目標です。
原価管理の課題は管理作業の複雑さと手間がかかる点

原価管理には多くのデータ収集が必要です。複数のプロジェクトが同時進行している時期は原価の正確な収集が難しいケースもあり、詳細で的確な原価計算には専門知識が必要です。以下に原価管理の難しいところをまとめました。
- 複数プロジェクトの原価収集の難しさ
- 分析に関する専門知識の必要性
- 継続的なデータ収集・分析・管理の難しさ
また、データ収集や分析、管理に難しさを抱えるケースもあります。このように原価管理には作業の複雑さと人的コストの面で課題があるといえます。
原価管理システムを導入した場合、複雑な原価計算の自動処理や、リアルタイムでのデータ管理が可能になります。
また、原価管理システムには、PDCAサイクルを支援する機能が組み込まれているため、プロジェクトの進行状況や原価状況の定期的なレビューも容易です。差異分析に関するさまざまなシミュレーションや将来的なコスト変動の予測や経営戦略の調整についても試算できます。
複数のプロジェクトがあるとき原価を正確に収集するのが難しい
複数の製品製造やプロジェクトが同時期に進行している場合、各プロジェクト原価の正確な収集・管理が難しくなるケースがあります。
とくに、経済環境や社会情勢の変化が大きな影響を与える環境下では、変動要因の把握のために競合他社のデータや外部要因に関わるデータの収集・分析も必要です。以下に複数のプロジェクトの原価把握が難しいところをまとめました。
- 人的・設備リソースの競合
- 部門やプロジェクトごとの労務費・間接費の配分
- 他社データ・外部要因データの収集と分析
間接費や労務費については、明確な配賦基準の設定が必要です。全社的に基準を統一することで原価計算の精度向上を図れます。
同時進行中の複数の原価管理や各種データの一元管理には、専用の原価管理システムの導入が推奨されます。
想定される損失や代替仕入れ先のコストの算出、他社動向についても収集・分析が可能です。プロジェクト別の原価の自動集計や、リアルタイムでの情報収集が可能になるため、各種変動による経営への影響分析や重要な方針策定をサポートできます。
原価計算は専門知識が必要なので属人化しやすい
原価管理には原価計算が必須であり、継続的かつ柔軟にデータを集積する必要があります。
原価計算には実際原価計算や標準原価計算のほか、業種に応じた直接原価計算、間接原価計算などの種類があり、企業の規模や業種、製品の特性などによって最適な方法が異なります。
また以下に原価計算の種類をまとめました。
- 実際原価計算:製品やサービスの製造に実際にかかったコストをもとに原価を算出
- 標準原価計算:設定基準に基づいて原価を計算
- 見積原価計算:製品製造前に必要となる材料、労務、経費などを予測して算出
- 直接原価計算:直接関連する費用(直接材料費や直接労務費)のみを原価として算出
- 間接原価計算:間接材料費、間接労務費、間接経費などを原価に含める算出方法
原価管理には専門性を要するだけでなく、人手がかかる点も課題だといえます。
また、対応できる担当者が限られ属人化の要因になったり、情報が一部に集中するといった点が課題になるケースもあるでしょう。
この課題に対して、マニュアルの整備やデータ・知識の共有だけでは対応が難しい面があります。
継続的な原価管理を維持し、動向の把握や変動リスクを予測して対策を立てるためにも、専用の原価管理システムが大きな役割を果たします。原価管理システムによって複雑な計算プロセスが自動処理され、また、リスク予測や利益見通しについてもより明確になります。
エクセル管理はヒューマンエラーを起こしやすい
エクセルやスプレッドシートなどのファイルベースで原価管理を行う場合、原価管理用テンプレートの使用やフィルター機能、グラフやチャートを使った視覚化など便利なツールもそろっていますが、一定の課題も含まれています。
日常的に使用しているファイルの使用は便利ではあるものの、入力ミスや関数の誤入力、データの不整合などのヒューマンエラーを完全に排除するのが困難な点です。
以下にファイルベースで原価管理を行う際の課題をまとめました。
- 入力・計算ミス、エラーの抽出
- ファイル管理の煩雑化
- リアルタイムでのデータ共有の難しさ
- セキュリティリスク
- 作業者の固定による人事リスク
ファイルベースでも原価管理は可能とはいえ、経年によるファイル管理の煩雑化やセキュリティ面の課題、何よりもデータ逸失の危険性を抱えています。また、事業規模の拡大や新規事業への参入に伴う原価構造の変化の際には対応が難しくなるケースも考えられます。
そのため、原価管理には専門的な管理システムの導入が推奨されます。原価管理システムを導入することでデータの正確性と一貫性、セキュリティ対策が確保され、各種エラーを大幅に低減しながらビジネスの拡張にも対応可能です。
原価管理は「ジョブマネ」で正しく管理・運用

企業が原価計算の精度を高めるためには、自動化機能やリアルタイムデータ分析が可能な原価管理システムの導入が推奨されます。一般的な原価管理システムの特徴を見てみましょう。
- 標準原価、実際原価、予算原価などの原価計算機能
- 基幹システムやERPからの自動データ収集
- 差異分析
- リアルタイムデータ分析
原価管理システムの自動処理により業務の効率化、正確な原価管理が実現します。原価計算の精度が向上することで経営判断の質の向上も可能です。
また、近年では原価変動リスクに対する迅速な判断や対応が困難なケースも多々ありますが、より正確なデータが経営方針をサポートするため、安定性が向上します。とくにリアルタイムでのデータ分析は、リスクの早期察知や適切な対策を講じる時間の確保のためにも非常に重要です。
クラウド型業務管理ツール「ジョブマネ」
原価管理を効率的に実施できる中小企業向けのクラウド型業務管理ツール「ジョブマネ」には、原価管理や工数管理、ToDo管理をはじめとする多様な機能を提供しています。
- リアルタイムな原価管理
- 標準原価と実際原価の差異分析機能
- PDCAサイクルのサポート機能
- 原価情報の入力による注文書の自動作成
- 統合管理システム
ジョブマネの原価管理機能では1つの売上に対して複数登録できるため、外注先が増えても正確に管理できます。プロジェクトの案件ごとに日々の利益率が自動で計算され、初期費用がかからず月額1,000円から利用可能です。
また、PDCAサイクルを効率的に回すための包括的な機能を提供しており、企業が業務改善を進める上で非常に有用なツールです。計画段階での予算設定、実行段階での進捗管理、評価段階でのデータ分析、改善段階での次のアクションの策定を支援します。
ジョブマネは、原価計算機能からバックオフィス機能まで備えており、原価管理だけでなく経費精算、工数管理、請求書発行など、業務に必要なさまざまな機能を一つのプラットフォームで提供しています。
売上に対して複数の原価を登録できるので正確に管理できる
ジョブマネの原価管理機能では、案件ごとに売上、仕入れ、外注費、工数、経費などの原価情報を一元管理できます。
プロジェクトの案件ごとに売上や外注費などのコストを紐づけて管理できるため、外注先が増えても正確な原価情報をトレース可能です。
日々の利益率が自動で計算され、モバイル端末対応であるため外出先でも原価情報の確認が可能です。
原価情報を入力するだけで注文書が自動作成される
ジョブマネでは登録した原価情報に基づいて自動作成する機能があるため、原価情報から自動的に注文書が作成されます。
また、売上や案件管理などのバックオフィス機能も備えているため、さらなる業務改善や人的資源の最適な配分調整も可能です。
正確な原価計算は、企業の成長と競争力を維持するために不可欠です。原価計算の精度を高めるためにも、原価管理システムの導入が推奨されます。専用システムを導入することで原価データの一元管理やリアルタイム分析による戦略的な原価管理が可能です。企業の成長を支える重要な選択肢として原価管理ツールを活用し、より堅実な経営計画を推進しましょう。